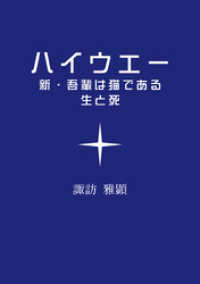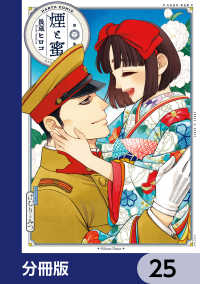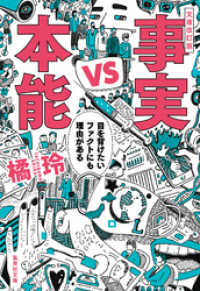出版社内容情報
21世紀に求められる流域管理、流砂景管理、集水域管理、景域管理の指針を示す待望の書き下ろし。
北アメリカ、ヨーロッパ、中国、北海道の釧路湿原などの先進事例、調査事例を紹介しながら、森林、河川、農地、宅地と分断された河川流域管理をつなぎ直すために、総合的な土地利用のあり方を提言する。
【書評再録】
●林政ニュース評(1999年8月6日号)=アメリカ、スイス、ドイツなどの先進的な河川管理手法を紹介しながら、総合的な土地利用のあり方を示している。
【内容紹介】本書「はじめに」より
この本のタイトルにもなった「流域一貫」あるいは「水系一貫」という言葉は、古くから多くの人々に使われている言葉ではあるが、現代においてもなお新しい響きを持ち、その重要性を訴えかけてくる。考え方の基本は中国治水史にさかのぼり、「黄河を治むるものは天下を治む」と言われてきた中国数千年の治水史には、流域を一貫してみる治水思想が流れている。
一方、近年直面する問題を扱うには、もはや流域という概念では狭くなっているのかもしれない。筆者が1997年から1998年に参画した河川審議会総合土砂管理小委員会の答申では、「流砂系」という言葉が使われた。流砂系とは、流域からの運搬物質が最終的に到達する海岸域も含めた言葉として定義され、まさに流砂が関与する流域の源頭部から海岸までを一貫して議論しようとしたものであった。流域から生産される土砂は、砂利採取や治山砂防ダム、貯水ダムなどの影響によって、河口まで供給されなくなってきている。このため、海岸部ではいちじるしい侵食を受け、消波ブロックによる防護を余儀なくされている。砂防と河川、海岸が別々に計画され議論されてきた現状を、流砂系の観点からつながりとしてとらえる必要性を宣言したものであった。
北海道では、流域の土地利用、とくに酪農によって生み出される糞尿や微細土砂が海域まで漂流し、漁業への影響が心配されている。そのためか、漁協婦人部の方々が山に土地を買い、植樹する運動を展開している。まさに、流域と海域のつながりである。さらに、世界をながめるとランドスケープ(landscape)という言葉が注目を集めるようになってきている。とくにアメリカ合衆国では、ランドスケープという言葉が、流域を越える概念として扱われており、日本でもこの意味から「景域」という訳語を用いる人もいる。鳥類相の保護などは、まさに分水嶺を越えた問題であり、生息場環境の保全のために、発達段階の異なる森林を、流域を越えて数百平方キロメートル単位のランドスケープ内でいかに配置するかなどが議論されている。
このように、流域やさらに大きな空間単位を表す言葉が学会だけでなく、行政でも一般市民のあいだでも用いられるようになってきた。その背景には、現在人類が直面するいわゆる「環境問題」が広域化し、その原因と結果のつながりが見えなくなってきていることがある。
水道から供給される水はどこから来るのか、さらに下水の水はどこへ流れていくのか、川とのつながりで理解している一般市民はほとんどいない。大量の木材を輸入する日本では、普段使用する紙の起源を日本の森林、もしくは世界の森林資源とつなげて考えることすらできなくなっているのである。本論のもう一つのテーマはこの「つながり」であり、みえなくなった森と川と人のつながりをもう一度見直す舞台が「流域」である。
【内容紹介】本書「おわりに」より
最近、北海道のみならず、本州で発生している地域問題についても相談を受けるようになった。相談相手は、時に行政に携わる方であり、時に一般の住民の方、コンサルタントの方、そして自然保護団体の方など、さまざまである。そして、これらの相談内容のほとんどが、一筋縄ではいかない難題である。難題である理由は、本論のテーマである流域のさまざまなつながりを介して発生しているためで、単純な因果関係では説明できない。また、バラバラに個々の現象に分解しても、システム全体を描くことはできないのである。本書が、見えなくなっている森と川と人間のつながりを理解するうえで少しでも役立ち、地域の流域保全に携わっている研究者、技術者、住民の方々に対して新たな視点を提供できれば、筆者としてはこのうえない幸せである。
【主要目次】
▲▲第1章・環境問題---その主体と議論のあいまいさ
環境の主体は何か(主体を明確に/2つの問題)
機能しなくなった現行のシステム(各分野に変化が/日本の文化に合った川づくりへ)
生態学は環境問題を解決できるか(社会的期待と要請/生物多様性で地域問題が解決できるか/地域からの出発)
▲▲第2章・流域保全に関する制度と技術---現状と課題
治水三法(低水工事から高水工事へ/省益は国益ならず)
保安林(17種類に分けられた保安林/単一機能論の落とし穴)
保全計画における時間の概念(確率概念/流域における土砂生産と流送の不連続性/環境保全計画)
▲▲第3章・森と川と人のつながりの変化
釧路湿原の事例(釧路湿原の概況/流域土地利用の変化/微細土砂流入の実態/河床の上昇と濁水の氾濫/セシウムによる土砂堆積の検証/湿原植生への影響/まとめ)
問寒別川流域の事例(洪水流量の増加/水辺環境の変化/まとめ)
▲▲第4章・新たなつながりの模索
アメリカ合衆国における森林河川管理(原生林と絶滅の恐れのある種/河川環境に与える水辺林の影響とその保護/New Forestryをめぐる論争)
スイス・ドイツにおける近自然河川工法(最初の疑問/補償・代償の考え方/土地利用との関連/工法的特徴/科学的根拠)
中国の総合治理(黄土高原の概要/黄家二岔小流域における土壌侵食と保全事業/総合治理)
日本の総合治水(都市型水害と総合治水/総合治水事業と流出抑制施設/伏籠川における流出抑制施設の役割/流域環境整備における流出抑制施設の役割)
▲▲結論・新たな視点
動的立地環境(物質の移動と流路の変動/渓畔域の地形と渓畔林/河川生態系維持のために)
物質の流れと生物生息場環境(景観生態学とは何か/物質の流れと生物生息場環境/on-siteの発想からoff-siteの発想へ/景観管理計画をめざして)
予測不可能な生態系の応答を前提とした管理(Adaptive management(適応可能な管理)とは/アメリカ合衆国におけるadaptive managementの事例/コロンビア川サケ科魚類保護の問題)
法的整備(日本の特殊性/ドイツの自然保護法/地方分権と中央集権)
情報公開と政策提案・決定機関の分離(不信はどこからくるのか/政策提案と決定機関の分離/責任の所在)
内容説明
本書は、21世紀に求められる流域管理、流砂系管理、集水域管理、景域管理の指針を示した。また、北アメリカ、ヨーロッパ、中国、釧路湿原などの先進事例、調査事例を紹介しながら、森林、河川、農地、宅地、と分断された河川流域管理をつなぎ直すために、総合的な土地利用のあり方を提言する。
目次
第1章 環境問題―その主体と議論のあいまいさ
第2章 流域保全に関する制度と技術―現状と課題
第3章 森と川と人のつながりの変化
第4章 新たなつながりの模索
結論 新たな視点