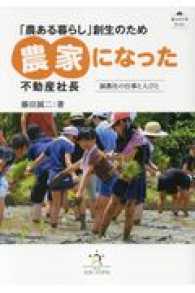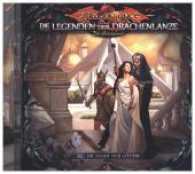出版社内容情報
日本の代表的な火山の成り立ち、地形、地質などを、実際に歩いて知るコース設定と解説。ハイカー・温泉マニアから防災関係者まで、幅広く使えるフィールドガイド。
★朝日新聞読書欄「知りたい読みたい」欄(2000年4月16日)=全国を五つの地域に分け、それぞれの代表的な火山を個別に解説している。コンパクトな装丁で、火山観光やハイキングのガイドとしても使える。
★熊本日日新聞評(1999年3月29日)=地質観察や防災からハイキング、温泉めぐりまで、フィールドガイドとして幅広く役立つ一冊。
★山と渓谷評(1998年10月号)=裏山にある活火山も、いつかは必ず噴火するという現実を認識し、火山をよく知るために書かれた本。それぞれの地形や火山活動史、地質観察に適した時期やポイントなどが紹介されている。
★教育新聞評(1998年9月20日)=「火山の種類」「年代測定法」「広域テフラ」などの火山用語も、囲みで解説されており、用語解説も詳しい。
●「はじめに」より=火山学者グスコーブドリが活躍したイーハトーブの国は、多数の火山が活動する火山国でした。このイーハトーブ国のモデルとなったのが、東北地方、なかでも岩手火山などがある岩手県だったのです。
東北地方は、多くの火山の恵みもうけています。豊かな湯量を誇るたくさんの温泉や、地熱発電、美しい景観などの観光資源がそれです。東京から東北新幹線に乗り盛岡にむかうと、宇都宮をすぎたあたりから、左手の脊梁山脈につぎつぎと優美な姿の火山が立ち現れます。日光、高原、那須、そして郡山から福島にかけては、磐梯、安達太良、吾妻、蔵王、仙台をすぎると船形、栗駒、焼石、そして盛岡に近づくと岩手と、一定の間隔をおいて火山が並んでいるのをみることができます。東北では、多くの場所で、身近な「ふるさとの火山」を仰ぎみることができます。東北と火山は、切っても切れない関係にあるといってもよいでしょう。
本書では、まず東北の火山についての概説をおこない、そのうえで、十和田、岩手、秋田駒ケ岳、鳥海、蔵王、吾妻、安達太良、磐梯、那須の各火山について取り上げています。
各火山の項では、地形図や交通に関する情報をしめした後に、観察するさいの注意事項や観察に適した時期が述べられています。それから、火山地形や噴火史の概説、それに温泉の紹介があり、その後に各観察地点の解説がしめされています。
本書には、フィールドの第一線で活躍するさまざまな研究者の方のこれまでの研究成果がもりこまれています。一般の方にも理解できるようにやさしく書かれてはありますが、内容の学術的レベルは決して落としてありません。
本書を手にして、火山のフィールドに出かけてみましょう。厳しくも美しい自然と出会い、温泉を満喫し、火山と直接対話することによって、その本当の姿にふれることができるはずです。
【主要目次】
東北の火山/9つの火山について個別解説(下記【収録した火山】を参照のこと)/用語の解説
【収録した火山】
十和田湖(巨大噴火のエネルギーを秘めた伝説のカルデラ湖)
岩手山(マグマうごめく東北の名峰)
秋田駒ケ岳(本州でもっとも新しい昭和の溶岩流をたずねて)
鳥海山(日本海側随一の巨大活火山をめぐって)
蔵王山(美しい火口湖に秘められた火山の素顔をさぐる)
吾妻山(雄大な爆裂カルデラと中央火口丘を歩く)
安達太良山(ほんとうの空の下で火山トレッキング)
磐梯山(村々を埋めつくした100年前の山体大崩壊)
那須岳(室町時代に噴出した溶岩ドームをめぐって)
内容説明
火山国日本初、本格的な火山ガイド。日本を代表する火山の成り立ちを歩いて知るコース設定と解説。ハイカー・温泉マニアから防災関係者まで、幅広く使えるフィールドガイド。本書では、十和田、岩手、秋田駒、鳥海、蔵王、安達太良、吾妻、磐梯、那須の東北地方の各火山を取り上げた。
目次
1 十和田火山―巨大噴火のエネルギーを秘めた伝説のカルデラ湖
2 岩手火山―マグマうごめく東北の名峰―成長と崩壊をくりかえす成層火山
3 秋田駒ヶ岳火山―本州でもっとも新しい昭和の溶岩流をたずねて
4 鳥海火山―日本海側随一の巨大活火山をめぐって
5 蔵王火山―美しい火口湖に秘められた火山の素顔をさぐる
6 吾妻火山―雄大な爆裂カルデラと中央火口丘を歩く
7 安達太良火山―ほんとうの空の下で火山トレッキング
8 磐梯火山―村々を埋めつくした100年前の山体大崩壊
9 那須火山―室町時代に噴出した溶岩ドームをめぐって
感想・レビュー
-

- 和書
- 保育園の園内研修