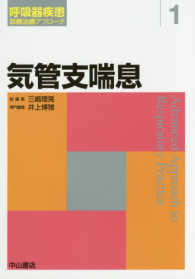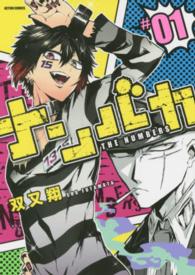出版社内容情報
本書の特徴1.「九州」が、日本列島や地球的な広がりと歴史の視点で解説されている。2.自然災害・防災に役立つ。3.環境問題を解決するための応用地質学の役割がわかる。 ●●●本書「まえがき」より=応用地質学は私たちの生活を豊にするいろいろな社会整備にも大きく関わっています。これらは、ダム、高速道路、上下水道に代表される“インフラ”と呼ばれるものです。ダムや道路を実際に造っているのは建設会社の技術者の方々ですが、工事に取りかかる何年も前にダムサイトや道路のルートを決めるために活躍しているのが、応用地質学の技術者なのです。最近では、廃棄物処分や地下水汚染などの環境問題にも地質学が応用されています。このように、応用地質学はあまり目立たないものですが、社会にいろいろな形で貢献しています。このたび、日本応用地質学会九州支部の創立20周年を記念し、地質学の一面を知っていただくことを願って、この本をつくりました。主に九州で活躍している人たちが書いたため、実例は九州ばかりですが、内容はどこでも通用するものです。この本を読んで応用地質学に少しでも興味をもっていただければ、望外の幸せです。●●● 【主要目次】▲▲第1章・自然の恩恵=火山の置きみやげ/サンゴ礁の贈りもの/黄金の島/石炭から始まった/こんなところに温泉が/地熱を求めて探す/地下水の物語/阿蘇が育てた熊本の地下水/鬼の洗濯岩/岩の造形 ▲▲第2章・地盤を調べて---社会資本のために=地盤を知る技術/ダムのいろいろ/隠れた地層/親ダム子ダム/地下に水を貯める/黒ダイヤとダム/トンネルと地盤/シラスを掘る/都会のモグラ/地域を結ぶ---橋/シラスにのせる橋/島を結ぶ橋/雲海を渡る橋/サンゴ礁にかける橋/竹馬に乗る/海辺の発電所 ▲▲第3章・自然を知り、災害を防ぎ、環境を守る=平成の島原大変/公園がすべった/北松の地すべり/地すべりを締めつける/出水を襲った“大蛇”/雨に弱いシラス/危険を知らせるハザードマップ/都市を襲う気象災害/“地震”を知る/地盤で変わる地震災害/活断層---地層に残された地震の記録 ▲▲第4章・より良い環境を残すために=地下水汚染/ヒ素汚染をつきとめる/ごみとつきあう/温泉街が沈んだ/サンゴ礁の危機---赤土汚染/石炭が残したもの---その功罪/炭鉱跡地のリサイクリング ▲▲第5章・明日の応用地質学=21世紀に羽ばたく君へ/自然環境を大切にする社会へ/これからの社会とともに/地質技術者から見た21世紀
内容説明
「九州」が、日本列島や地球的な広がりと歴史の視点で解説されている。自然災害・防災に役立つ。環境問題を解決するための応用地質学の役割がわかる。
目次
第1章 自然の恩恵
第2章 地盤を調べて―社会資本のために
第3章 自然を知り、災害を防ぎ、環境を守る
第4章 より良い環境を残すために
第5章 明日の応用地質学