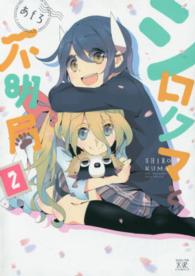出版社内容情報
三峡ダム建設をめぐる日本と世界のハイドロ・マフィアの実態を究明。三峡ダム建設の問題点--住民移住、堆砂、ダムの安全性、歴史・文化遺産の保護、資金問題を詳細に検証。河川の合理的管理から離れ、ダム建設自体が自己目的化した「巨大ダム開発の世紀」の終焉を予感させるレポート。 ★★★エコノミスト評(1997年10月28日号)=三峡ダムをめぐる世界各国の巨大建設会社、三峡ダム建設の現状をあますところなく描写した力作。★★★東方評(1998年4月号)=巨大水力工事の影に暗躍する世界と日本のハイドロ・マフィアの実態に迫ろうとしている。★★★ ●●●「まえがき」より=「ハイドロ・マフィア」は、これを定義づけるならば、ダム、発電所、灌漑などの水関連事業を食い物にする暗黒組織網であるということができよう。この闇の世界は、コンサルタント会社、ゼネコン、重電機メーカー、商社などを中心に、これに金融界が絡み、さらに官界、政界が関与する形で形成されている。また、これらと深く結びついた専門家、学者、研究者、評論家なども、アドバイザー的役割ないしはスポークスマン的役割を演じている。このような政・財・官・学の癒着構造は、何もハイドロ・マフィアに限られているわけではない。その地下組織網は、経済活動のあらゆる分野に広がっている。その意味では、広くは「開発マフィア」ということができよう。このような「開発マフィア」は、官僚政治および利権政治と深く結びついて、腐敗と汚職の政治構造を生み出し、近代市民社会の在り方を大きく歪めてきた。本書において究極的に狙いとしているのは、三峡ダム問題を通じて、ハイドロ・マフィアの実態を解明することである。しかし、ハイドロ・マフィアは、地下組織を通じて暗躍するため、その活動の実態についての情報を入手することは、非常に難しい。調べれば調べるほど、暗黒の世界の奥深さに愕然とするばかりである。ハイドロ・マフィアの伏魔殿のヴェールを完全に剥ぎ取ることは、至難の業である。とはいえ、三峡プロジェクトでは、ハイドロ・マフィアは、その私益追求の強引さと焦りの故に、闇の姿を、一部ではあるが顕在化させている。この点を究明すること、つまり三峡ダム建設を食い物にしようとする日本および外国のハイドロ・マフィアの実態を究明することが、本書の目的の一つである。もう一つの目的は、三峡ダムの主要問題点--住民移住問題、堆砂問題、ダムの安全性の問題、歴史的・文化的遺産の保護問題、資金問題など--について、それらが、はたして克服可能なのかどうかについて検討を加えることである。●●● 【主要目次】▲▲第1章・三峡ダム構想とは=長江と治水/三峡ダム建設構想 ▲▲第2章・ハイドロ・マフィアの動向=世界のハイドロ・マフィアの動向/日本のハイドロ・マフィアの動向/発電機をめぐる受注戦争 ▲▲第3章・ハイドロ・マフィアに奉仕する輸銀と通産省=国会議員とNGOを欺いた輸銀と通産省/輸銀と通産省のデタラメな調査報告書 ▲▲第4章・住民移住問題=「開発型移住」指針/住民移住の実情 ▲▲第5章・堆砂問題=「蓄清排渾」/長江の土砂含有量は、増えていない?/卵石、礫石は動かない? ▲▲第6章・ダムの安全性の問題=仮ダムの安全性/山崩れ、地滑り、土砂崩れの問題/ダムの耐震性 ▲▲第7章・歴史的・文化的遺産の保護問題=破壊されつつある史跡/三峡の歴史的・文化的遺産/三峡ダム建設と文化財保護/建前と実行の違い ▲▲第8章・資金問題=「釣魚プロジェクト」/ダム建設は、資金的に続くのか? 資料=三峡プロジェクトに関する日本輸出入銀行の調査結果とコメント/「人権アセスメント実施要求項目」に対する日本輸出入銀行の回答とコメント/文化財保護に関する江沢民総書記と政治局常務委員会への書簡
内容説明
中国の大河を600キロに渡ってせきとめる三峡ダム建設。このメガプロジェクトを巡る日本と世界のハイドロ・マフィアの実態を究明。三峡ダム開発の問題点―住民移住、堆砂、ダムの安全性、歴史・文化遺産の保護、資金問題―を詳細に検証。河川の合理的管理から離れ、ダム建設自体が自己目的化した「巨大ダム開発の世紀」の終焉を予感させるレポート。
目次
1 三峡ダム構想とは
2 ハイドロ・マフィアの動向
3 ハイドロ・マフィアに奉仕する輸銀と通産省
4 住民移住問題
5 堆砂問題
6 ダムの安全性の問題
7 歴史的・文化的遺産の保護問題
8 資金問題