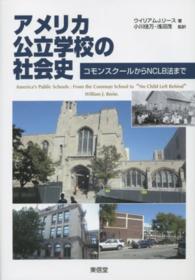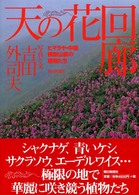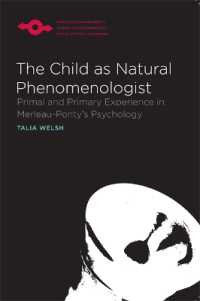出版社内容情報
土木・建設関係の技術者をめざす人びとのために、特に、その基本となる地質学の問題を整理し、体系化させた入門書。実際の現場で活用できるように、基礎編と応用編にわけ、多くの図表をまじえてわかりやすく解説する。 ●●●本書「あとがき」より=有能な土木家と接してみると、彼らは、地質学そのものというよりは、その説明で理解される地質構造が、自分のたずさわる建設計画・構造物とどうかかわりあうかを考えることが主要な問題で、地層の成り立ちの歴史から、岩層の強度が地下でどう変化しているか、断層などの分離面・弱線が構造物とどのような関係にあるかなど、自らの頭の中で考察されているようでした。現場での地質の説明の中で、質問の多くは、どうしてこのような地質分布となるか、説明の根拠・理由などにかかわるものでした。この入門書は、地質技術者が、土木工学の分野でどんな発想で地質調査を行っているか、地質学的な発想の基本を述べている内容が多く、いわゆる地質学的な学問の先端などを紹介するつもりはありません。人間生活の向上を目指す土木建設、その基礎となる土木工学の基本は大地の上で行われるということです。したがって大地に関する知識が無いと土木建設は成り立たないことは自明のことでしょう。この入門書は、工学者に、大地に関する知識に興味をもっていただくための最初の手引書といったところです。●●● 【主要目次】▲▲基礎編=自然と人間/偉大な自然の力/人間の偉大な営み/地質学の歴史/地質調査結果の利用/地質学の基礎知識(その1)/地質学の基本原理/地質年代/地層命名規約/地質学の基礎知識(その2)/岩相区分と時代区分/土粒子の大きさ/地層の対比/地質の諸現象/地層の接触境界/山腹のクリープ/基底礫岩(層)(Basal conglomerate)/節理(Joint) ▲▲応用編=地質調査結果の表現/調査資料/写真/地層境界/岩石と岩盤/鉱物(Mineral)/火成岩(Igneous rock)/堆積岩(Sedimentary rock)/変成岩(Metamorphic rock)/岩石の破壊強さ/岩(岩盤 Rock Mass)/岩盤区分/空中写真の利用/沖積層(軟弱地盤)/沖積層の成り立ち/軟弱地盤/地盤沈下/江戸から東京へ/地盤の液状化/地すべり/地すべり現象/地すべり崩壊時期の予測/地すべり崩壊時期の予測方法/地質調査法/調査の目的/調査法の種類/日本の地質概要
内容説明
本書は、生産や建設に直接結びつく地質学・土木地質学とは何か、についての講義内容をもとに、広く土木技術関係の人びとに対し、地質学がどのように土木建設や環境問題にアプローチできるかという事柄を、多くの図表をあげて解説した。
目次
1 基礎編(自然と人間;偉大な自然の力;人間の偉大な営み;地質学の歴史;地質調査結果の利用;地質学の基礎知識;地質諸現象)
2 応用編(地質調査結果の表現;岩石と岩盤;空中写真の利用;沖積層〈軟弱地盤〉;地盤の液状化;地すべり;地質調査法;日本の地質概要)