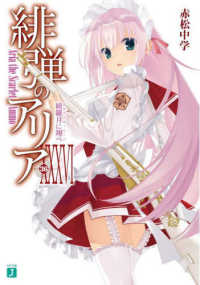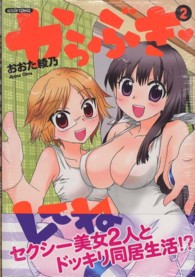出版社内容情報
無敵のアマチュアリズムで、第一級の化石標本6000点。
化石採集の名人となった著者が伝授する化石採集のヨロコビとその極意。
巻末には、化石採集のコツ、化石産地869ヶ所、展示施設157ヶ所の一覧表付。
【書評再録】
●中日新聞評(1994年9月17日)=化石との出会いから底無しの魅力までを、具体的な体験を交えて紹介している。喜々として採集旅行に出かける気分、思わぬ収穫の喜び、体験で感じた問題提起などが素直につづられており、一気に読み通せる。
●日刊ゲンダイ評(1994年9月2日)=化石採集の喜びとその極意におのずと触れることができる。採集の準備から標本づくりまでの懇切丁寧なノウハウ、日本全国863ヶ所に及ぶ化石産地一覧、展示施設紹介など、付録・資料が特に充実。
●子供の科学評(1996年9月号)=著者の実体験からにじみでた自然観などがそれとなく折り込まれていて、楽しく読みすすめながらもいろいろと教えられることが多い本です。化石を勉強したい人たちへの親切な配慮がなされているのもうれしいことです。
【読者の声】
■男性(41歳)=数々の素晴らしい化石標本の写真と親近感あふれる旅の文章によって、化石に興味を持っている私にとって、本当にワクワクさせられる本です。
■男性(44歳)=全国的に化石産地が網羅されていて内容が充実している。
■女性(23歳)=化石標本の写真がみごとでした。特にアンモナイトの内部構造と題された写真。本来なら中に何かつまっていて見えない部分の写真。この一枚の写真で、取り寄せてまで購入しようという気になりました。
■男性(33歳)=単なるガイドブックでなく、読み物として楽しく読ませてもらいました。
【内容紹介】本書「はじめに」より
琵琶湖の東部、彦根市にある僕の家の二階からは、青い山脈・鈴鹿山脈がすぐそこに見える。僕の愛する霊仙山は鈴鹿山脈の一番北の山だ。中学のときにこの霊仙山に化石採集に行って以来、この山の化石に魅せられ、以後28年間の長きにわたって研究を続けている。
そもそも、化石採集などというものは、多分に宝探し的な要素をもっていて、他人よりも先に、しかも、よりめずらしいものを手に入れようと必死になる。冒険あり、探検ありの男の世界といってもいいかもしれない。そんな世界にのめり込み、とうとう人からは、インディ・ジョーンズみたいな奴だといわれ、褒められているのか、バカにされているのか。しかし、一度化石採集のおもしろさを知ったら、ちょっとやそっとではやめられないものがある。
わが国のような小さな国土で、1億2000万もの人口を抱える超過密国では、最近、ますます化石が採りにくくなってきた。僕の住む琵琶湖の周辺も、開発がどんどん進んで家や工場が建ち並び、かつて、たくさん化石を産出した場所がどんどんなくなってきている。そんな状況の中でも、時々、新聞やテレビを賑わすような化石の発見がある。そんなニュースを耳にしたり目にすると、僕は、あたかも自分がその遠い過去の世界、地質時代に生きているような想像をしてしまうのである。
昔から何かを集めることが好きで、切手に始まり、シール、コイン、鍵、バッジ、キーホルダー、マッチ箱など、比較的子供でも手に入れやすいものを集めてきた。しかしながら、切手は大変なお金がかかるし、あとのものは集めてもたかが知れている。それにこんなものは誰でも持っているもので、そうたいそう感激もないことから、しだいに興味は薄れていった。しかし、集めるということは生まれもった性格のようで、鉱物に始まり、いつしか6000点近い化石のコレクターとなってしまった。
僕が公務員という安定した職場を捨てて早5年が経とうとしている。はやりの脱サラか? と思いきや、その後企業に就職するわけでもなく、自分で商売を始めたわけでもない。世間から見れば気楽な身分、はたまた遊び人とも思われがちだ。
しかし、たった一度きりの人生を、好きなことをして生きるのが一番、ただただそう信じてこの5年間を過ごしてきた。めずらしい化石に出会って興奮し、大雪山の自然とふれあって感激し、生活は決して楽ではないが、心の中は充実感で満ち溢れている。
この5年間、いろいろなことをやってきたが、この際、僕の化石人生を自己紹介し、化石の楽しみ、化石の不思議をぜひとも広く一般の方々に知っていただこうと思い、筆を執った次第である。この本は、そんな僕の化石への思いを、旅人ともにまとめたものである。
第1章では僕が化石と出会い、その美しさ、不思議さに魅了されていった経過を、第2章では、社会人となってからも化石に夢中になり、数々の発見をしていく様子を述べたものである。そして第3章では、長年勤めた仕事を辞め、晴れて自由人となってから現在に至るまでの化石人生をお話したい。
付録として、僕の長年の経験をもとに化石採集のノウハウ、整理方法をまとめてみた。また、全国の化石産地は自分の足で歩いた産地に加え、さまざまな参考資料をまとめあげたものだ。しかし、化石産地は絶えず変化しており、今ではすでに採集不可能となった場所や、採集禁止になっている場所もあるのでご承知願いたい。化石を収蔵・展示している施設は、国立の博物館から市町村の資料館まであらゆる施設を網羅した。僕は旅に出る都度、心がけて見学するようにしているが、数が多くてまだ半分もまわっていない。化石専門の博物館もあると思えば、専門外で少ししか展示していないところもあるが、なるべく多くの施設を掲載した。以上付録としてはたいそうなものになってしまったが、きっとお役に立つであろう。
【主要目次】
▲▲第1章・化石との出会い
▲小学生時代……方解石との出会い
▲中学生時代……化石との出会い・鉱物から化石へ
▲高校生になって……初めて権現谷へ
▲「原色化石図鑑」と出会って……胸が熱くなる
▲憧れの金生山……日本の古生物学の発祥の地
▲「サンゴ山」の発見……狙いどおりの大発見、危うく遭難
▲竹馬の友・村長衆治君……スピリファーの発見者
▲福地のハチノスサンゴ……憧れの地・その1
▲日本一周自転車旅行・化石産地を訪ねて その1……今しかできないから
▲村本さんを訪ねて……アンモナイト人生40年
▲犬頭山の貴州サンゴ……憧れの地・その2
▲葛生の米粒石……憧れの地・その3
▲横倉山のクサリサンゴ……憧れの地・その4
▲吉川勇二君との出会い……金生山にて
▲日本一周自転車旅行・化石産地を訪ねて その2……再び旅に
▲祇園山のクサリサンゴ……憧れの地・その5
▲壱岐の魚化石……時化のときは化石の魚を採る漁師・平田善義さん
▲▲第2章・化石に魅せられて
▲社会人となって……年貢の納めどき
▲古見のカニ化石……団塊とノジュール
▲瑞浪のサメの歯……初めてのサメの歯
▲隠居山……デスモスチルスの里
▲中央自動車道……瑞浪化石博物館
▲初めての化石展……東海化石趣味の会
▲三種の神器……三葉虫、アンモナイト、サメの歯
▲2回目の北海道……アンモナイトと光主さん
▲足立敬一君との出会い……弟子誕生
▲愛車ジムニー……拡がった活動範囲
▲講師に招かれて……先生の先生
▲服部川のワニの歯……出し抜きの発見
▲鮎河のツリテラ……執念の発見
▲柳谷のカルカロドン……間違いの発見、けがの功名
▲2回目の化石展……化石を返して!
▲鮎河のビカリア……偶然の発見
▲木ノ浦の植物化石……紫水晶とともに
▲珪化木……準・三種の神器
▲神戸のヒトデ……電車に飛び乗って
▲甲賀町のドブ貝……田んぼの中で
▲古琵琶湖層の魚化石……一日三体、お魚デー
▲昔は海やった……説明の難しさ
▲25年間のまとめ……『滋賀県自然誌』
▲憧れ、感動、満足感、好奇心……心が騒ぐ、心が躍る
▲▲第3章・自由人となって化石の奥深さを知る
▲公務員よサヨウナラ……したいことをしながら生きたい
▲上八瀬の三葉虫……印象化石
▲野洲川のゾウの足跡化石……時代は違えど、同じ土地に住む
▲大雪山のナキウサギ……生きた化石
▲阿南町のサメの歯……一日で140個
▲アオイ貝……地球の異変?
▲奈義町のビカリア……圧力に負ける
▲北海道に通いつめて……熊に脅えながら
▲ユウパキディスカス採集記……初めての大物
▲近江カルストの化石……三葉虫三昧
▲鋸山のオキナエビス貝……サメの餌食だったか?
▲自然破壊と自然保護……地球はむしばまれている
▲化石は採集するべし……節度ある採集を!
▲夢、希望……自然史博物館
▲浦河のハウエリセラス……久し振りの収穫、しかも大物が
▲亘理町のカルカロドン……化石採りが化石にならないように
▲▲付録
▲化石採集のノウハウ
1.準備
2.見つけ方
3.採集の仕方
▲化石の整理方法
1.クリーニングの方法
2.整理の仕方
3.プレパラートを作ろう
4.化石の写真を撮ろう
▲全国の化石産地一覧
▲化石を収蔵・展示している施設一覧
内容説明
無敵のアマチュアリズムで、第一級の化石標本6000点。化石採集の名人となった著者が伝授する化石採集の“ヨロコビ”とその極意。巻末には、化石採集のコツ、化石産地869カ所、展示施設157カ所の一覧表付。
目次
第1章 化石との出会い
第2章 化石に魅せられて
第3章 自由人となって化石の奥深さを知る
付録(化石採集のノウハウ;化石の整理方法;全国の化石産地一覧;化石を収蔵・展示している施施一覧)
感想・レビュー
-

- 和書
- 下田直子の編み物技法