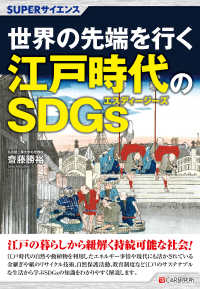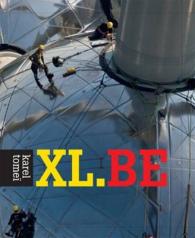出版社内容情報
世界のいずれの地にも見ることのできない謎の神火「不知火」の歴史的考察も含め、その発生のメカニズムを30年にわたる実験と現地調査にもとづいて解明する。 ★★★熊本日日新聞評(1994年11月21日)=古くから諸説が入り乱れ、謎とされてきた不知火についての集大成ともいえる本。★★★歴史読本評(1995年1月号)=日本独特の自然現象といわれながらも絶滅しつつある不知火を科学分析し、その語源や古代からの歴史についてまとめた、まったく新しい案内書。★★★ ●●●本書「序文……中村純二氏」より=「不知火」現象は干潟の位置や形、大きい潮の干満差、適当な風速で吹く視線方向の風、海面上の気温分布など、様々な自然条件が重なって初めて見られる、世界でも稀な天然の光屈折現象である。近年、不知火海にも埋立工事や川と海の汚染等、様々の環境破壊が押し寄せ、干潟や海水温に変化を生じ、年々不知火現象が現れがたくなってきているのは誠に残念である。本書をきっかけとして、不知火海の環境保全が積極的に行われ、このロマン溢れる南海の風物詩が存続し、次代にも伝えられていくことを、切に祈って止まない。●●● 【主要目次】▲▲第1章・不知火とは何か=神秘の不知火/万葉集と不知火/国語辞典における不知火の解釈/歴史における不知火の登場/白髪山の怪火/火の国と不知火/火邑の蜃気楼/「不知火」とは何か/諸方面における不知火の原因解明 ▲▲第2章・不知火の実態=昭和11年における宮西先生の研究/第2回の宮西先生の調査/その他の不知火観察/宮西先生のユニークな諸調査/宮西氏による不知火の形態的分析/不知火海(八代海)の自然環境 ▲▲第3章・不知火の研究=見えなかった不知火/不知火現象についての専門的諸解説 ▲▲第4章・実験によるアプローチ=実験を思い立つ/宮西先生の実験/現地調査よりの判断/自然状況を加味しての実験/ついに発見した実験装置での不知火現象/分火観測のための装置/シュリーレン写真の撮影/総合不知火観測実験装置/熱源長と分火幅との関係/温度差と分火幅の関係 ▲▲第5章・不知火をとらえる=不知火海における自然状況--視線方向の連続温度に関連して/不知火の実体について/不知火の発生/考えられる不知火発生の原因/広大な州平原の起こす異常気流/視線方向の風による縦型気層の出現 ▲▲第6章・不知火現象の気象的機構=寺田先生による層流発生の実験/熱板上に層状気流の発生を見るための実験/不知火発生原因の総合的判断/不知火発生時の不知火海周辺の自然及び人為的環境 ▲▲第7章・まとめとして--関連諸現象など 付録・計算による分火現象へのアプローチ=実験と調査よりの推定/平行空気層における入射光の屈折/空気の屈折率と温度の関係/垂直気層の温度勾配/気層の有効長と屈折幅との関係/実験例と計算値との対比/不知火海の場合
内容説明
古来から秘火とされてきた不知火は、世界で例を見ぬ自然現象だが、環境の悪化により消滅に向っている。著者は30年にわたる研究調査の上、この神秘的な現象が、たての積み重ねの気層による蜃気楼に対し、よこに積み重なった気層により生じるとして解明した。
目次
第1章 不知火とは何か
第2章 不知火の実態
第3章 不知火の研究
第4章 実験によるアプローチ
第5章 不知火をとらえる
第6章 不知火現象の気象的機構
第7章 まとめとして―関連諸現象など
付録 計算による分火現象へのアプローチ