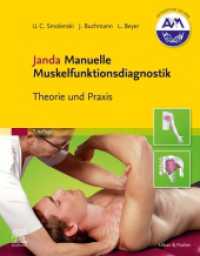出版社内容情報
★千葉日報評(1992年6月30日)=この本は、身近な自然をたずねて、その自然に親しみ、自然を知ってもらおうと、県内11ヶ所を紹介している。文章も分かりやすく、案内図や露頭図・写真なども豊富。休日の自然観察のガイドブックとして推奨したい。
■女性(17歳)=写真・絵・図がついてて分かりやすい。身近な地域のことで、余計、分かりやすくていい。地学系が嫌いでもこれなら読める。
●本書「まえがき」より=地球規模の環境破壊が大きな問題とされ、46億年の地球の歴史のなかで、現在の人間活動が、緑豊かに保たれつづけてきた地球を、ここ100年で変えようとしている。便利さを求め、使い捨てを当然とする感覚が、自然環境を美しいと感じ、大事に守っていこうとする心を失わせているように思う。
身近な自然環境でおこっている環境の変化は、直接、私たちの生活と密接するだけに、環境維持には深い関心をもち、正確な理解が必要となる。それには、まず自然の実態を十分に知ることであり、そのうえで人間の営んできた生活との関わりの観点で考え、さらに著しい開発にともなった人工改変の立場から自然を見つめることが大切である。この本は具体的に千葉を例にして、それぞれの地域別に、歩いて自然から学ぶゆきかたをとっている。地形や地質など自然の実態を、その場所での露頭観察で読み取ったり、縄文や万葉の昔のなぎさを地形から学んだり、自然の改変によってもたらされる影響の深さなどを示してくれている。
また、地盤に関する地震災害が、地域の地質環境にどう関係していたか、0m地帯を残した地盤沈下による公害が、地下水、天然ガス採取とどう結びついているか、資料や証拠をもとに勉強してもらいたい。とくに、貴重な資源である地下水や天然ガスを、あとあとの子孫のためにも、良好な状況で保持しつつ、環境に影響を与えないような調和ある有効利用を志すことが大事であろう。
千葉の自然への理解をすすめ、この本を手がかりに、さらに深く自然の本質を求めて歩かれ、身近な環境を大切に残していく努力を期待したい。
【主要目次】
縄文の海、万葉の入江(市川・浦安)/古東京湾のなごり(花見川・印旛沼)/
ニホンムカシジカのいた里(市原)/東京湾最後の干潟(小櫃川デルタ)/
移り変わる海岸線(館山)/地震の爪あとと笠森層(松尾・成東・東金)/
古東京海底谷をのぞく(上総湊)/天然ガス・ヨード・温泉(茂原・養老川の上総層群)/
踊る地層(鋸山の三浦層群)/海洋底からの訪問者(嶺岡・鴨川の火成岩類)/
地層の博物館(銚子の中生層を中心に)
資料=貝化石分布図/植物化石分布図/哺乳類化石分布図/博物館分布図
目次
1 縄文の海、万葉の入江―市川・浦安
2 古東京湾のなごり―花見川・印旛沼
3 ニホンムカシジカのいた里―市原
4 東京湾最後の干潟―小櫃川デルタ
5 移り変わる海岸線―館山
6 地震の爪あとと笠森層―松尾・成東・東金
7 古東京海底谷をのぞく―上総湊
8 天然ガス・ヨード・温泉―茂原・養老川の上総層群
9 躍る地層―鋸山の三浦層群
10 海洋底からの訪問者―嶺岡・鴨川の火成岩類
11 地層の博物館―銚子の中生層を中心に