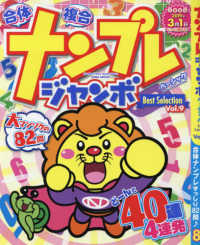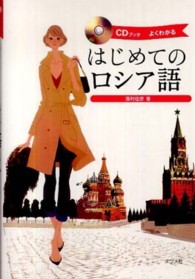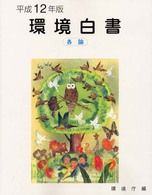内容説明
常陸国、播磨国、出雲国、肥前国、豊後国…謎と不思議にみちあふれた「ご当地」の古代史。『風土記』一三〇〇年!「記・紀」には記されない神話の世界。
目次
第1章 『風土記』の世界編(『風土記』って何だろう?;土蜘蛛とは何か? ほか)
第2章 『風土記』の神々編(朝鮮半島にゆかりのあるアメノヒボコとは何者か?;オオクニヌシと国を造った小さな神スクナヒコナとは? ほか)
第3章 『風土記』と神社編(出雲大社の建立は「国引き」の後?「国譲り」の後?;伊勢神宮と伊勢国とはどのような関係にあるの? ほか)
第4章 『風土記』の成り立ち編(『風土記』はどのような人によって編まれたのか?;『風土記』の成立年代は? ほか)
第5章 『風土記』散歩編(万病が治る「神の湯」と呼ばれた!?玉造温泉;出雲国の神名火山の役割とは? ほか)
第6章 全国「風土記の丘」編(山形県立うきたむ風土記の丘;しもつけ風土記の丘 ほか)
著者等紹介
瀧音能之[タキオトヨシユキ]
1953年、北海道生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。現在、駒澤大学文学部教授、島根県古代文化センター客員研究員、博士(文学・早稲田大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
おゆ
8
全ての章が図版込み2〜4ページに纏められていて、読み味の軽いコラム集といった印象。「風土記の世界編」は記紀ファンにはおさらい程度の内容、「全国風土記の丘編」はいっそ表でよいのでは?という定形ぶり。けれど神々編、神社編は各章短いながらも発見があり面白かった。こんなにアメノヒボコ推してる本初めて読んだよ。記紀の内容や神名をある程度おさえていて、風土記との差異を楽しみたい私程度の入門者には、軽めの案内書として重宝します。さりげなく交通アクセスも逐一載せてくれているので、散策の手引きにも良さそう。2017/07/20
ぽんくまそ
8
記紀とは違う異質さにあふれた出雲国風土記を手に、出雲を回ったときは楽しかった。常陸国風土記は「春は花咲き、秋は紅葉。常陸よいとこ一度はおいで」という自画自賛な調子だったのが良かったのか読破できた。播磨国は初めの方で挫折。肥前国と豊後国は手をつけていない。なら、この手の入門書タイプからいこうとしたが、手分けをして書いているのが専門家たちなので、どうにも固い。謎が解かれるどころか、ますます謎が深まって行く。2016/01/26
かいちゃん
3
風土記についての解説本。 中央政府編纂が、古事記、日本書紀とするならば、風土記は地域密着型ということらしい。 出雲風土記がほぼ全文残っているそうだが、播磨風土記も確認すると、この2箇所、割りと関係が深いように見える。 しかし、この手の本は、ストーリー性を持たせることがなく、読みにくいし、伝えたいことが分かりにくい。 というか、あまり分からなかった(T_T)2015/04/10
みっちぃ
2
似た内容のものを寄せて章立てしているけれど,そもそもが様々な研究者の書いた解説文(1つあたり2~4ページ)を寄せ集めている感があって,深く掘り下げて読み解くという感じではない。 神々編は面白かった。 あと,冒頭のところだったか,風土記に見る各地の特産品のところで,こんな昔からフグを食していたのかと驚き(笑)チャレンジャーは古に存在した。2025/02/05