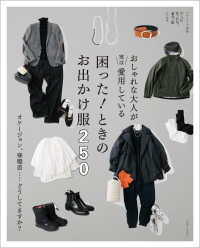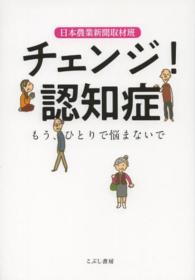内容説明
長い歳月のなかで育まれてきた食べものに目を向け、食生活を変える(カタカナ食から日本食に戻る)ことが、健康への第一歩。風土から生まれたバラエティに富む伝統食で、元気なからだを取り戻す。
目次
第1章 FOODは風土の原点―日本縦断徒歩旅行
第2章 ほろびゆく長寿村・棡原との出合い
第3章 現代の食生活の乱れはカタカナ食が増えたせい
第4章 「県民食」のいろいろ(ごはん―主食のいろいろ;めん類;みそ;汁もの;常備食)
著者等紹介
幕内秀夫[マクウチヒデオ]
1953年茨城県生まれ。東京農業大学栄養学科卒業。管理栄養士。フーズ&ヘルス研究所代表、学校給食と子どもの健康を考える会代表。山梨県の長寿村を知って以来、伝統食と民間食養法の研究をおこなう。日本列島を歩いて縦断や横断などを重ねた末に「FOODは風土」を提唱。保育園、幼稚園の給食改善、社員食堂の指導、プロスポーツ選手の食事指導などをおこなう(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
6
もー、病気になっているので、これ以上悪化させないように、ということかな。塩のおかげで農海産物が無駄にならずにきた日本(42頁)。私の地方にも伝統食すんきが塩不足で発酵食品が浸透したというので納得。カタカナ食でなく、和食に回帰すれば健康回復するというのも同感。通訳案内士日本地理や一般常識でも知っておく内容かもしれない。2013/04/25
Humbaba
3
ハレの日とケの日.メディアに露出が多いのは圧倒的にハレの日だが,実際に生活をしている時に多く出会うのはケの日である.その時の食事というのは特別なものではないが,だからこそ伝統的な知が凝集されているとも言える.2012/12/02
いえのぶ
1
管理栄養士で伝統食と民間食療法を研究する著者が、日本全国の昔から食べられている日常食についてごはん、麺、みそなどに分類してわかりやすくまとめている。2019/01/14
-

- 和書
- 人間の本質と自己実現