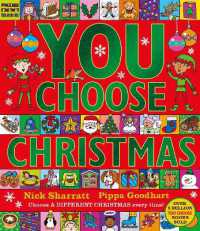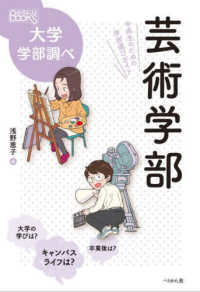内容説明
当世のドラマに世阿弥の“花伝書”はどう反映されうるか?演劇評論家・河内厚郎が語る“平成風姿花伝”気鋭のユニークな論考をお楽しみあれ。
目次
1 「花」のいのち
2 「気」は「機」なり
3 死と真実
4 言葉の海へ
5 場に宿る神々
6 都市という劇場
7 日本の楽劇、その将来
著者等紹介
河内厚郎[カワウチアツロウ]
1952年、西宮市生まれ。甲陽学院高校卒。一橋大学法学部卒。演劇評論家として執筆活動に入る。’87から月刊「関西文学」の編集長をつとめる。夙川学院短期大学教授。(財)阪急学園・池田文庫理事。羽曳野市民大学・学長。「関西・歌舞伎を愛する会」代表世話人。「宝塚映画祭」実行委員長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
0
<芸の「花」> 世阿弥の時代 「花狂い」多かった 「肝要、此道は、ただ花が能の命なる」 花(華)のない人は、売れない 文筆でもそう いつもワンパターン 常間の芸 =芸がない <衆人愛敬> 見巧者 寿福=多くの人を幸せな気分にする 久田舜一郎氏=能小鼓・大倉流 友人 <虚業のダイナミズム> <ものをおもう> 神 男 女 狂・・・4番目 = 物狂い 鬼 「恋重荷」=老人の片思い <ドラマとしての能> 碁(源氏物語から)という能 空蝉 軒端の萩 いかなる交渉があったのか、癪だが、2008/12/30
-
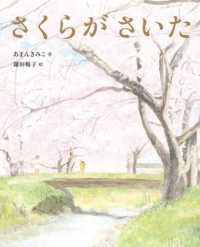
- 和書
- さくらがさいた