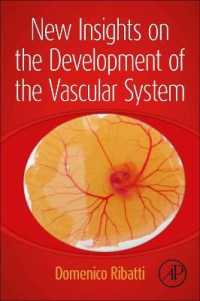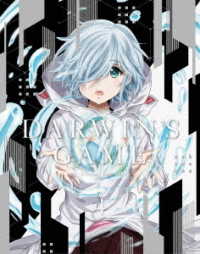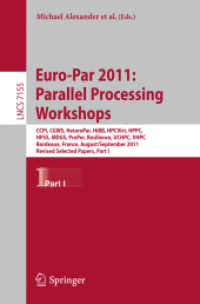内容説明
若者支援の中核を成す7つのテーマについて、それぞれの要点を「かかわり方」まで具体化し解説しています。専門機関につながる方法や本人とのかかわり方、家族問題への介入、経済問題への介入など、臨床現場で編み出された実践的技術です。「かかわり方」の実際を、100を超える事例で紹介します。テーマ間の関係や時間の経過に伴う変化・影響は、フルイラストの長編事例が臨場感豊かに描き出します。
目次
第1章 専門機関につながる方法
第2章 本人とのかかわり方
第3章 家族問題への介入の仕方
第4章 経済問題への介入の仕方
第5章 居場所の確保の仕方
第6章 恋愛、結婚、出産への向き合い方
第7章 自立に向けた支援
著者等紹介
西隈亜紀[ニシクマアキ]
関西学院大学文学部卒業、日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科博士前期課程修了。毎日新聞社に入社し、いじめや不登校、障害児教育、虐待などの教育・福祉問題を追いかけるなか、精神保健福祉に関心を抱き、臨床家への転身を決意。退職して精神保健福祉士の資格を取得し、精神科ソーシャルワーカーとして医療法人社団新新会多摩あおば病院に入職。2013(平成25)年、12年勤めた病院を退職し、心のケアを必要とする若者のためのグループホーム「キキ」を設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヒデミン@もも
37
著者西隈亜紀さんの優れた人柄が随所に感じられる。西隈さんのようなSWに出会えた患者、後輩は幸運。あとがきによるとやはり自身も思春期・青年期は嫌になるほど不安定だったらしい。思春期のトンネルに入り、中は真っ暗で先も見えず、自分の存在自体がわからなくなりそうな恐怖。自分の存在を確かめるために他者を求める。そうやって、かなり長い時間を経て自立し大人になるのを支えてくれたのは、家族よりも他人の力が大きい。いろんな人に出会えたからこそ自立できた。2016/06/17
ゆう。
11
精神保健福祉士を主な対象とした本で、how-to本という感じのものです。著者もソーシャルワーカーの援助技術はマニュアル化できるものではないが、あえてマニュアルのように書いたと述べています。事例が多く、その事例に対してどのような援助技法があるのか書かれているのですが、著者の経験主義的な論述が多く、クライエントの生活問題が見えにくいという感じがしました。1つの方法論だなという視点で読めば役に立つかもしれません。2014/09/26
ソーシャ
2
PSWの著者が、心理的な問題を抱えた思春期・青年期の若者の支援の実際をわかり易く解説した入門書。出会いから恋愛、結婚、出産、就労支援といった実務上問題になるところまで著者の支援の方法や考え方が具体的な事例とともに解説されていて、この本自体が青年期精神医療がどんなふうに行われているか知る上でとてもいい入門書になっています。実際に困る点なども正直に書かれているあたりに著者の人柄を感じますね。2023/08/11
オラフシンドローム
1
★★★☆☆ 援助者に必要とされる資質 という見出しに惹かれたのですが…。 言葉にすると当たり前のことを、どこまで客観的に、愚直におこなえるか、が大切なのだろうなと思う。2024/10/08
-

- 電子書籍
- 河本景 【増量版 全50P】ヤンマガア…