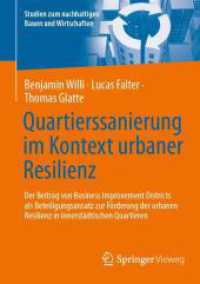- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学外科系
- > リハビリテーション医学
目次
第1章 高次脳機能障害を越えて(高次脳機能障害とはどういった障害なのか;高次脳機能障害とリハビリテーション;障害の受容と無理解)
第2章 高次脳機能障害者の生活を支える(生活支援に必要な高次脳機能障害への視点;私が介護に望むこと)
著者等紹介
山田規畝子[ヤマダキクコ]
1964(昭和39)年、香川県高松市生まれ。東京女子医科大学在学中に最初の脳出血を起こし、持病モヤモヤ病が発覚。後遺症なく卒業し、整形外科医として同大付属病院に勤務。26歳で郷里高松に戻り香川医科大学(現・香川大学医学部)に勤務。その後、実家の山田整形外科病院の院長となって間もない33歳のとき、脳出血により脳梗塞を併発、高次脳機能障害に至る。それでもリハビリ医を目指し、愛媛県伊予病院に勤務するが、37歳で三度目の脳出血。半側空間無視など新たな後遺症が加わったが、姉が運営する介護老人保健施設の施設長として社会復帰を果たす(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かいちゃん
25
前に読んだ山田さんの本もよかったですが、これは特によかったです。 高次脳機能障がいのこともよくわかるし、周りにどうして欲しいのかも具体的でわかりやすく書いてありました。 想像を働かせる、大事なことですね2024/08/01
まこ
4
介護者への注文 よかれと思って片付けても、本人の法則性を崩すので暴力となる。 介護者がよかれと思ってしたことも本人の自宅なんだから、本人の自由。 だとしたら、私は暴力受けてきたと思う。 介護者には想像力を磨いて介護してほしいと私も思う。2021/11/04
iqo720
0
高次脳機能障害を持つ家族には勇気と希望をくれる本。 「脳は進化し続ける」という言葉に救われるとともに、 頑張っていこう!という気にさせてくれた。 途中途中被害妄想的というか、 「想像力があればそんなことはしないのに・・・」 というくだりが続くのは気になったが、 患者目線ではそのように思うのだろう。 本から学んだことをいかしていきたい。2012/03/03
AiTaka_twi
0
★★★☆☆2011/12/31
kozawa
0
難病にて脳出血によって高次脳機能障害となった著者が語る世界。。。。難しい。2011/10/27
-
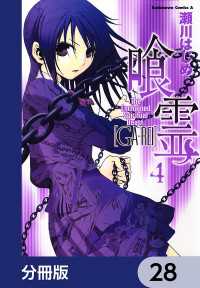
- 電子書籍
- 喰霊【分冊版】 28 角川コミックス・…