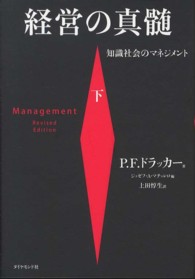出版社内容情報
経済思想の正しい理解のために!1870年代から1914年にかけての新古典派の貨幣経済学、特に貨幣数量説の展開を研究した第一級の学説史。研究者、経済政策や金融政策の決定者に。
内容説明
本書は、1870年代から1914年にかけての新古典派の貨幣経済学、特に貨幣数量説の展開を研究した第1級の学説史であるが、経済思想史の研究者あるいは貨幣経済学の研究者のみに読まれるのではなく、経済政策決定者、特に金融政策の決定に携わる政策決定者にも熟読して頂きたい書物である。
目次
第1章 概観
第2章 1870年代の正統派
第3章 物価水準についての新古典派理論―ケンブリッジ学派とフィッシャー
第4章 新古典派の景気循環論における貨幣的要素
第5章 ウィクセルと数量説
第6章 新古典派貨幣理論と貨幣制度
第7章 要約
著者等紹介
レイドラー,デビッド[Laidler,David]
1938年、イギリスのタインマウス(Tynemouth)で生まれ、1959年、ロンドン大学卒業。1960年、シラキューズ大学でMAを取得。1964年、シカゴ大学でPhDを取得。1961年、ロンドン大学を皮切りに、カリフォルニア大学バークレー校、エセックス大学で教鞭を執り、1969年から1975年までマンチェスター大学教授を勤め、1975年からウエスタン・オンタリオ大学教授。イギリスにおけるマネタリズムの先駆者の1人として知られインフレーションについての研究、特にマネタリストの観点からのインフレーションの研究者として有名。著書に『貨幣とインフレーションについての試論』(共著、1975年)、『貨幣の経済学』(1969年)、『現代マネタリズムの潮流』(1982年)等多数ある。後者2点については我が国でも翻訳され『貨幣の経済学』については、スペイン語版(1972年)、フランス語版(1975年)、イタリア語版(1976年)も出版されている
栗田善吉[クリタゼンキチ]
主要業績『最適規制-公共料金入門』(共訳、文真堂、1998年)。『現代日本経済の課題』(共著、税務経理協会、2000年)
横溝えりか[ヨコミゾエリカ]
主要業績『東アジア諸国の貿易収支と対外債務の持続可能性』(産業経営、第26号、1999年)。『現代日本経済の課題』(共著、税務経理協会、2000年)
石橋春男[イシバシハルオ]
大東文化大学経済学部教授
嶋村紘輝[シマムラヒロキ]
早稲田大学商学部教授
関谷喜三郎[セキヤキサブロウ]
日本大学商学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。