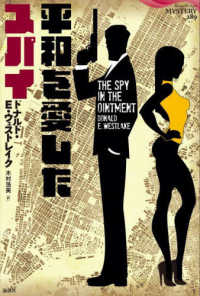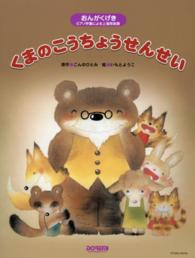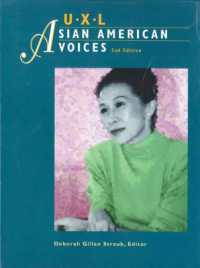- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
内容説明
発達障害のある子どもたちが起こす「行動問題」。「妹の髪を引っ張る」「教室の電気を消す」「床に寝そべる」など、その状況はさまざまです。「行動問題」には、本人にとって起こさざるを得ない理由があります。「なぜ」を探り、その理由に対応した支援の方法を見つけることが「行動問題」の根本的な解決につながるのです。本書では、「行動問題」の解決に最も効果をあげている応用行動分析学の理論と技術を、豊富な事例をとおしてやさしく学べます。
目次
第1章 人が行う行動の理由を探る
第2章 生活を豊かにするアプローチ(上手なきっかけのつくり方;行動の理由に適合した対応方法;行動問題を起こさない環境のつくり方;自分の行動のマネジメント;子どもをやる気にさせる手立て)
第3章 包括的なアプローチ
著者等紹介
小笠原恵[オガサハラケイ]
東京学芸大学教育学部特別支援科学講座准教授。臨床心理士。臨床発達心理士。自閉症を中心とした発達に障害のある子どもたちへの臨床を中心に研究を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
香菜子(かなこ・Kanako)
32
発達障害のある子の「行動問題」解決ケーススタディ―やさしく学べる応用行動分析。小笠原恵先生の著書。発達障害のある子供たちが行動問題を起こすには理由があります。行動問題を起こす理由や行動問題への対処法がわかりやすくまとまっている良書です。保護者や教師に限らず、発達障害のある子供と接する機会がある人すべてにとって参考になる内容です。2018/12/28
Natsuko
14
応用行動分析について著者をかえて2冊目。当然と言えば当然だが、理論やアプローチ法については1冊目と変わらず。どちらも障害を持った人と関わる人に対して優しいスタンスなのがいい。著者の小笠原氏も、問題行動があっても、本人のせいでも保護者のせいでも教員のせいでもない、一人一人にアセスメントしオーダーメイドの支援計画をたてる優しい学問と述べておられる。 本作は、事例ごとに実践的なアプローチ法と基づく理論に分かれて書かれている。 理論だけを通して読んでみても効果的と思われる。 2019/08/22
るい
4
本当にわかりやすく、応用行動分析が学べる本。事例もよくあるものが用いられ、具体的に書かれているので、子どもがどういう結果を求めて問題行動を起こしているのかや、どのような目標や代替行動を挙げればいいのかがわかる。この考えを用いていきたい。2016/04/21
ひろか
1
タイトル通り。架空の事例への介入を検討することを通してやさしく応用行動分析が学べる。事例の後は簡単な理論的な説明がされている。2011/05/28
ocean
0
個人攻撃の罠に陥らないこと。 こだわりは性格をあらわすことで、行動の理由になりえない。 つまり、どれも環境に起因しているということ。これを忘れずにかかわっていこうと思いました。
-
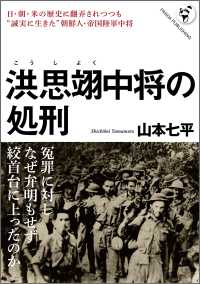
- 和書
- OD>洪思翊中将の処刑