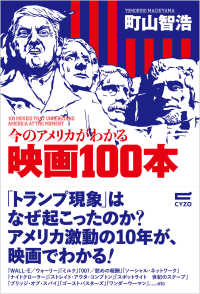内容説明
「環境保全活動」として急速に広がりつつあるケナフ栽培やビオトープづくり、身近な自然を取り戻そうと放流されるメダカやホタル。しかしこれらの行為は、かえって環境破壊につながってしまうこともある。それはなぜなのか。では、どうしたらいいのか。本書は、生物多様性保全の視点から生き物を扱うルールについて掘り下げ、今後の自然体験活動のあり方を提案する。
目次
序章 ちょっと待ってケナフ!これでいいのビオトープ?
第1章 なぜケナフは注目されているの?
第2章 広がるケナフの輪
第3章 ケナフの疑問―帰化の危険性
第4章 ケナフは本当に地球に優しいか?
第5章 外来種って、何?
第6章 国際的に保全が叫ばれている生物多様性
第7章 善意が引き起こす環境破壊
第8章 これからの体験活動を考える
著者等紹介
上赤博文[カミアカヒロフミ]
1955年、佐賀県牛津町生まれ。1979年、広島大学理学部生物学科(植物学専攻)卒業。1988年、鳴門教育大学学校教育研究科(自然系理科)修了。1979年4月に佐賀県で教職の道に入り(生物教諭)、白石高校、佐賀西高校を経て、1997年4月より佐賀県教育センター研究員。本業の教職のかたわら、佐賀県内の植物群落、植物(フロラ)を調べ、特に佐賀平野のクリークの植物は10年近く調査している。また、県内のレッドデータ植物を調査することも多く、今日、保全生態学についての関心が最も高い。専門は、植物生態学と植物細胞遺伝学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fumikaze
7
これは読んでみて良かった。庭にビオトープを作りたく、つい野草を近所から持ってきたり、知人のビオトープ管理士の人から庭でホタルやヤゴを育てる事を勧められてその気になっていたが、この本を読んで思いとどまった。/ 先ずは環境を整えてから自然に生き物が来てくれるのを待ち(原則として自然の遷移に任せ)、生き物他所から連れてくる場合はきちんと調べてからにしなければいけない。/ ビオトープと学校ビオトープとは別物。学校ビオトープとは子供達への教育の場として、自然体験をさせる為のもの。2025/09/25
Hiroyuki Nakajima
2
どちらも環境保全に役立つものと考えがちですが、ケナフは野生化して生態系に影響を与える危険があり、ビオトープも元々の生態を再現した作りでなくては、単なる自然庭園となって外来種の生物の繁殖を助け近隣の生態系にダメージを与えかねない事がわかりました。人が手を加えつつ自然を守る難しさを感じます。池などの閉じた水域に長期間生息していたヘイケホタルの生息地に他の地域からホタルを持ってくると遺伝子撹乱が起こってしまうと言う事は思いもよらず、勉強になりました。またゲンジボタルは川などの開いた水域に生息すると言うことも始め2011/11/28
Acha
1
勉強本。なんとなく、じゃだめだからなー。2011/05/29