内容説明
かつて戦争は国策追求の手段だった。そんな時代の論理と心理。
目次
第1部 世界大戦とどう向き合ったのか(欧洲大戦と日本のゆらぎ;三つの「戦争」―満洲事変、支那事変、大東亜戦争;第二次世界大戦―アジアの戦争とヨーロッパの戦争;南進と大東亜「解放」)
第2部 軍人はいかに考えたのか(朝鮮駐屯日本軍の実像―治安・防衛・帝国;帝国在郷軍人会と政治;日本陸軍の中国共産党観―一九二六~三七年;日本軍人の蒋介石観―陸軍支那通を中心として;戦前日本の危機管理―居留民保護をめぐって)
第3部 中国となぜ戦い続けたのか(支那事変初期における近衛内閣の対応;日本人の日中戦争観―一九三七~四一年;日中和平工作の挫折;汪兆銘のハノイ脱出をめぐって―関係者の回想と外務省記録から;桐工作をめぐって;対中和平工作 一九四二~四五年)
著者等紹介
戸部良一[トベリョウイチ]
防衛大学校名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授。1948年宮城県生まれ。京都大学法学部卒業、同大学院法学研究科博士課程単位取得退学。博士(法学)。防衛大学校教授、国際日本文化研究センター教授、帝京大学教授などを歴任。著書に『ピース・フィーラー』(論創社、吉田茂賞)、『自壊の病理』(日本経済新聞出版、アジア太平洋賞特別賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
フンフン
4
いくつか新知見があった。とくに朝鮮駐屯日本軍の実像については知らないことが多かった。2021/10/08
Hisashi Tokunaga
1
「失敗の本質」「逆説の軍隊」以来の戸部氏の著作を読んだ。門外漢で素人の私にとって日中の「事変」(日本にとっての)の経緯をたどる事は大変な労力が必要だった。ともかくも日中間には戦争開戦の詔勅はなかったようだ。それでも中国は戦勝国の仲間に与した。満州事変以降の定かならない中国政府はまるで維新前の日本の様だ。薩長なのか、幕府なのか、朝廷天皇なのか・・・どこが政権の中心なのか?そして、日本は何のための戦争(事変)なのかさえも変質していく様がいささかでも感じ取れた私でした。2021/11/03
DBstars
0
全体として膨大な量の一次史料を用いている。政策文書や議会想定答弁を多用し政府方針の形成や変容に主眼を置く一方で、陸軍新聞班史料、日記や書簡、論文を引用し、個人の主張や思考を検討する箇所もある。「確定できない部分が少なくない」、「試みには限界があり、また偏りが生じることも避けがたい」(203-204頁)とあるように、史料の限界に挑戦した貴重な研究なのだと感じる。 十五年戦争論を取らないことは著者の重要な主張である。個人的には3つの戦争に連続性を見出しており、再考するきっかけとなる論説である。2023/10/13
-
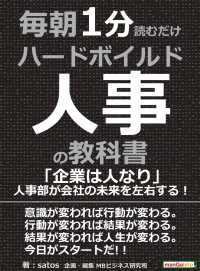
- 電子書籍
- 毎朝1分読むだけハードボイルド人事の教…








