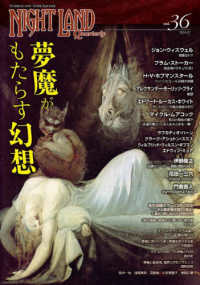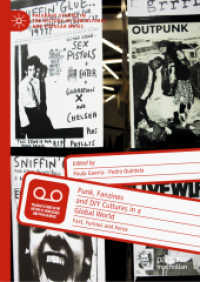出版社内容情報
昭和14年発行の稀覯本に沢木老師の貴重な写真と「老師の言葉」を加え復刊!「只管打坐」を世に蘇らせた沢木興道老師の原点の書!
【目 次】
第一章 坐禅の意義
一、参禅学道は一生の大事
1 自分と無関係の坐禅
2 群を抜けて益なし
3 坐禅は、ただするもの
4 創造のない生活
二、坐禅は禅門の第一義
三、坐禅の当体そのまま仏身
1 人々仏法の器
2 坐禅の神秘
3 偏えに随順する
4 仏を体現する
四、生活即坐禅
1 仏道を生活する
2 修行の真偽
3 形の上の鍛練
4 仏祖の道の外に禅なし
第二章 坐禅にかかるまで
一、道場の選び方
二、道場の整え方
三、身体の整え方
第三章 坐禅の身構え(調身)
一、覚触すること
二、足の組み方
1 結跏趺坐の作法
2 半跏趺坐の作法
三、手の置き方
四、降魔坐と吉祥坐
五、正しい姿勢
1 坐蒲の敷き方
2 坐禅の際の口
3 坐禅の際の目
4 坐禅の際の呼吸
5 左右揺振
六、起坐の儀則
七、経行の儀則
八、坐禅中の心の置き場所
九、眠い時にはどうするか
第四章 坐禅の心構え(調心)
第五章 僧堂進退の心得
一、後夜坐禅
二、初夜坐禅
三、開枕
四、早晨坐禅
五、僧堂の規矩
正法眼蔵 重雲堂式
六、聖僧について
七、その他の進退について
1 洗面
2 洗浄
3 入浴
普勧坐禅儀
附一 行鉢の仕方
応量器 十 喫 食
一 下 鉢 十一 再 進
二 展 鉢 十二 収 生
三 十仏名 十三 香湯浄水
四 粥時斎時の偈 十四 洗 鉢
五 行 食 十五 折 水
六 五観の偈 十六 収 鉢
七 生飯の偈 十七 打 槌
八 食三分の偈 十八 後唄文
九 ?鉢の偈 十九 施主の供養ある場合
薬石の作法
附二 沢木興道老師の言葉
澤木 興道[サワキ コウドウ]
明治13年、三重県津市の生まれ。幼くして両親を亡くし澤木家の養子になるが、17歳で永平寺へ。坐禅と勉学に打ちこみ、笛岡凌雲方丈や法隆寺勧学院に学び、熊本の万日山に独居して、乞われるまま全国の坐禅会を巡る。駒澤大学教授・総持寺後堂等うけたすべてを用いて只管打坐を勧め、昭和40年、京都安泰寺で遷化。享年86歳。『禅談』『禅を語る』『禅の道』『永平広録を読む』等(以上、大法輪閣)。
内容説明
道元・瑩山・大智・白隠らの坐禅についての要文を引用し、坐禅の意義・身構え・心構えを綿密に説く。何ものをも求めない道元禅師の坐禅「只管打坐」を世に蘇らせた沢木老師の原点!昭和14年発行の稀覯本に、新たに老師の貴重な写真と「沢木興道老師の言葉(坐禅について)」を加えて復刊。
目次
第1章 坐禅の意義
第2章 坐禅にかかるまで
第3章 坐禅の身構え(調身)
第4章 坐禅の心構え(調心)
第5章 僧堂進退の心得
附1 行鉢の仕方
附2 沢木興道老師の言葉(坐禅について)
著者等紹介
沢木興道[サワキコウドウ]
明治13年三重県津市に生まれる。名は才吉。明治20年両親・叔父の逝去後、津市一身田の提灯屋・沢木文吉の養子となる。明治29年家出して、徒歩で永平寺へ。明治30年熊本県天草の宗心寺沢田興法の下で出家得度、沢木興道となる。明治33年名古屋の歩兵第33連隊に入営。後に日露戦争で瀕死の重傷を負う。明治39年除隊。明治41年法隆寺勧学院に入り、佐伯定胤大僧正に唯識を学ぶ。大正元年三重県松坂の養泉寺僧堂の単頭となる。大正5年熊本の大慈寺僧堂講師に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rigmarole
とりさん