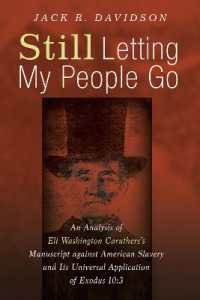- ホーム
- > 和書
- > ビジネス
- > ビジネス教養
- > IoT・AIビジネス
内容説明
生成AIの背景→生成AIの種類、AIの歴史など。生成AIの技術→深層学習の要素技術、生成AIの要素技術など。生成AIの活用→生成AIの活用事例、生成AIのリスク・対策など。生成AIをビジネスに活かすには、その背景や技術の基本知識が必要です!
目次
1章 生成AIとは何か
2章 AIの歴史
3章 機械学習の要素技術
4章 生成AIの要素技術
5章 生成AIの活用
6章 生成AIのリスクと対策
7章 生成AIの未来
著者等紹介
南龍太[ミナミリュウタ]
東京外国語大学卒。元共同通信社記者、現在、通信大手のシンクタンクにてAIや6GといったICTトレンドを調査・分析。その傍ら、国際NGO世界未来学連盟(本部パリ)日本支部代表として「未来学・未来洞察」の普及に取り組む。Newsweek日本版やNewspicksなどで記事を執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
28
生成AIをビジネスに活かたいと考える人向けに、生成AIを取り巻く背景とそれを支える技術といった基礎知識をキーワードから解説した1冊。生成AIとはどのようなものか、第1次から第4次ブームに至るまでの生成AIの歴史、機械学習の方法にはどのようなものがあるか、生成AI関連の技術とその相関関係、各分野で生成AIがどのように使われているのか、生成AIのリスクと対策、生成AIの進化まで、キーワードを見開き1ページで図解入りで解説していて、実践的な使い方の解説はありませんが、全体像を把握するにはいい1冊だと思いました。2024/05/04
くらーく
6
ITの仕事に就いたことも無いし、今は無職の身だけど、なぜか読んじゃうんだなあ。常識だものね。 どうして、生成AIが動いているのかを少しでも知っていると、何か良い事があるんじゃないかと思って、つらつらと。 目次のような問いを、実際に生成AIに聞いたら、どんな回答が来るのだろうね。誰かやっていないかしらねえ。そもそも、本書もそうやって(生成AIを使って)作られていたりしてな。その内、疑いを持つこと自体が無意味な時代が来るのかねえ。今、書いている感想は、生成AI不使用ですよ。2024/06/29
Tomitakeya
2
AIはスマホとかに普通に導入されている。Google検索しても使われている。それがどのように動いているか、どのような仕組みなのかはよくわからない。そもそもスマホやパソコンがどのように動いているかなんで、知らなくても使える。いわゆるブラックボックスだ。AIもそんな感じだ。それでも、仕組みを表面的にでも知っておいて損はないと思う。そういう内容だ。2026/01/14
にゃーごん
2
カラーで図が多く、端的な説明で辞書的に使えそう。書籍で読んだけど検索しやすいように電子で持っておくとよさそうだな。2024/11/10
kaz
1
深い内容までは理解できていないが、何がキーワードになっているかを知るうえで、非常に有益。図書館の内容紹介は『生成AIの基礎がわかる! 生成AIの種類、歴史、要素技術や応用サービス、活用事例、法規制などを解説。見開き左ページにはテキスト、右ページにはイラストや写真、図を掲載して視覚的なわかりやすさを重視した構成』。 2024/08/14