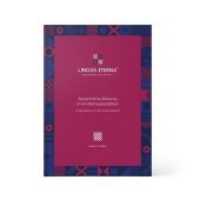目次
第1章 ゲージはどうして決められたか
第2章 19世紀の狭軌機関車
第3章 山を登る
第4章 高性能化への模索
第5章 日本国産機とドイツ製機
第6章 狭軌の挑戦
第7章 最終期の蒸気機関車
第8章 蒸気機関車の未来形
駆け巡った日本の覇者C62
著者等紹介
齋藤晃[サイトウアキラ]
1931年東京生まれ。慶応義塾大学経済学部卒業、日産自動車(株)及びその関連会社に勤務。在学中戦争で休眠した鉄道研究会を復活、そのOB会である鉄研三田会の事務局長、会長を経て現在相談役。退職後著作活動を続ける。著書『蒸気機関車の興亡』NTT出版(1997年交通図書賞)、『蒸気機関車200年史』NTT出版(2008年第1回島秀雄記念優秀著作賞)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。