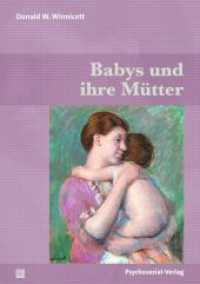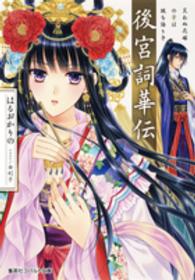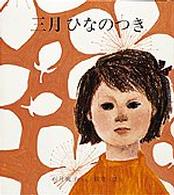内容説明
2011年、故郷喪失の追悼行事を封じ込める「ナクバ法」がイスラエルで成立した。ユダヤ人迫害を背景に建国されたイスラエルと、それゆえに郷土を破壊され奪われたパレスチナ人。両者の間には、いかなる共存の未来も存在しないのか―そして過去については?ユダヤ人とアラブ人双方の学者・作家19名が協同し、ユダヤ・中東史の深層を読み解きながら、政治的・歴史的分断を超えて語るための方法を探求する。
目次
第1部 ホロコーストとナクバ―新たな政治的・歴史的語法を可能にする諸条件(ユダヤ人とパレスチナ人を襲った災厄の前触れ―ヨーロッパの国民国家建設とその有害な遺産 一九一二‐一九四八年;ムスリムたち(ショアー、ナクバ) ほか)
第2部 ホロコーストとナクバ―歴史とカウンターヒストリー(コワルスキー夫妻が歴史に挑戦したとき―ジャッファ、一九四九年 ホロコーストとナクバのあいだ;荒れ狂う波に向けて上げた大胆な声―パレスチナ人知識人ナジャーティー・スィドキーと第二次世界大戦時のナチの教義に対するその闘い ほか)
第3部 ホロコーストとナクバ―トラウマ的シニフィアンの展開(記憶の文化―レア・グルンディヒとアベド・アーブディーの作品におけるホロコーストとナクバのイメージ;マアバラ―ショアーとナクバのあいだのミズラヒーム ほか)
第4部 エリヤース・フーリー『ゲットーの子供たち―わが名はアダム』について―ホロコーストとともにナクバを語る(対位法的読解としての小説―エリヤース・フーリーの『ゲットーの子供たち―わが名はアダム』;沈黙を書くこと―フーリーの小説『ゲットーの子供たち―わが名はアダム』を読む ほか)
著者等紹介
バシール,バシール[バシール,バシール] [Bashir,Bashir]
イスラエル・オープン大学政治理論准教授、ヴァン・レール・エルサレム研究所上級研究員。主な研究テーマは、ナショナリズムとシティズンシップ研究、多文化主義、民主主義理論、和解の政治学など
ゴールドバーグ,アモス[ゴールドバーグ,アモス] [Goldberg,Amos]
エルサレム・ヘブライ大学教授。ホロコースト研究・教育に従事。主な研究テーマは、ホロコーストにおけるユダヤ人の文化史、ホロコーストの歴史記述、グローバルな世界におけるホロコーストの記憶など
小森謙一郎[コモリケンイチロウ]
武蔵大学人文学部教授。専攻は、ヨーロッパ思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。