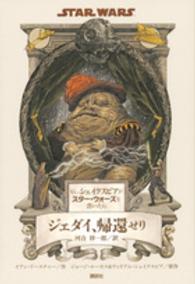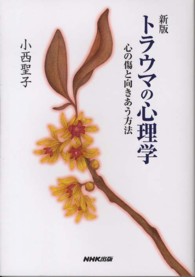内容説明
生涯作家を魅了したアントネッロ・ダ・メッシーナの“傭兵隊長”。その贋作をめぐって、「意識の流れ」の系譜も汲みながら、描かれる殺人逃走劇。作家が「最後まで書き上げることのできた最初の作品」と語り、死の直前まで、失われたことを悔やみ続けた事実上の処女作。
著者等紹介
ペレック,ジョルジュ[ペレック,ジョルジュ] [Perec,Georges]
1936年、パリに生まれ、1982年、同地に没した。小説家。1966年にレーモン・クノー率いる実験文学集団「ウリポ」に加わり、言語遊戯的作品の制作を行う
塩塚秀一郎[シオツカシュウイチロウ]
1970年、福岡県に生まれる。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学、パリ第三大学博士(文学)。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。専攻、フランス文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
105
アントネッロ・ダ・メッシーナが描いた「傭兵隊長」が表紙。ペレックなので、恐る恐る頁を開くと、「マデラは重かった。……段差ごとに両足が跳ね…」と大変読みやすい。これは、贋作者の告白、哲学論。贋作者はゴースト。上手いほど大家の作品に溶け込んでしまう。報酬というものでしか、自分は認められない存在。手に負えない作品を前にした時に、贋作者はどうなるだろうか。本人の芸術への探求、自己の肯定欲求が高まると、彼の存在意義自体が問題となる。芸術について鑑賞以外を求めない私にはあり得ない欲求だが、彼の苦悩はよくわかった。2016/08/09
きゅー
13
贋作者ガスパールは贋作販売の出資者を殺す。彼はなぜ自分の庇護者を殺したのか。彼の思考は十数年前に贋作づくりを始めた頃まで遡る。前半はガスパールの独想に占められており非常に読みづらい。読み進めて分かってくるのは、贋作者であることの息苦しさ。他の誰かに成り代わって生きることで、自分自身を見失ってしまっていた。本作は、ペレックの作品群の最初期のものでもあり、非常に尖った印象を受けた。後期の軽やかさは感じられないが、これはこれでねっとりとしたペレック体験を楽しめると思う。2017/03/28
みみみんみみすてぃ
8
これはかなり面白いです。ペレックの『人生 使用法』がいつも行っている図書館のフランス文学コーナーにあって「分厚いなあ……」と眺めるだけでしたが、ペレックの魅力に一気に惚れました。笑 もう亡くなっているのね…… 実験的、印象に残って離れない書き出しから、頁を捲っていく手が止まらない。2016/10/19
qoop
5
しがらみのない孤児であることを選びながらも与えられた自由の内で満足し、物質的充足と反比例する未成熟のままとどまり、贋作家として何者でもないまま日を送った主人公の、象徴的な親殺し。関係性の希薄さ、絵画表現と乖離していく自分自身、形成しきれないままの自己同一性、即物的な会話の中で浮かび切れない動機。若書きと云えばそうかもしれないが、充分魅力的な物語だった。2017/02/08
nranjen
4
先日プレイヤードから革張りのペレック全集が発売されたが、その中には入っていないこの作品。初期の作品その他全集からもれているものは多いらしい。しかし著者本人のこの作品への思いは強かったらしく、第三者の評価とわかれるところ。その「思い」はなぜ強かったのか、著者がここで試みたかったことは何だったのかが気になるところ。2017/07/06