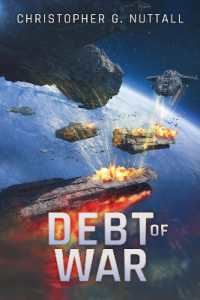出版社内容情報
長年大阪のフィールドワークを重ね、2013年に大阪高低差学会を設立した新之介さんによる、大阪の高低差地形散歩本。スリバチ学会の皆川さんの寄稿も含み、スリバチ本の地図デザインや構成に準じる形で、大阪を舞台とした地形散歩本。
内容説明
大阪はこんなにも凸凹だった!古墳、大阪城、道頓堀…謎とドラマに満ちた地形エンターテインメント。見て楽しい、歩いて楽しい、12エリアの凸凹マップ付。
目次
1 大阪の地形の魅力 高低差概論(砂州の上にできた大阪;母なる上町台地の記憶;地形歩きの極意)
2 大阪の高低差を歩く(大坂のはじまりの地;上町台地の高低差巡り;水辺の跡に誘われて;古代の海岸線を辿る)
特別寄稿 見せてもらおうか、大阪の「坂」とやらを(皆川典久)
著者等紹介
新之介[シンノスケ]
1965年大阪市淀川区生まれ。本業は広告会社のクリエイティブ部門に所属。2007年よりブログ「十三のいま昔を歩こう」を運営。十三にとどまらず、大阪全域の歴史や町歩きレポートを執筆。2013年、大阪高低差学会を設立。大阪の歴史と地形に着目したフィールドワークを続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hiro
73
著者の新之介さんはブラタモリの大阪編に案内人として登場された方。タモリさんも愛読しているという、この『大阪高低差地形散歩』を読んでみた。ブラタモリでも登場した崖下の八軒家船着場から南方向へ、また森ノ宮駅から西方向へ、それぞれの上町台地を上っていく坂は通勤等に利用していたが、結構な坂道だ。平らなところ多い大阪市内では異質な上町台地はタモリさんじゃないが大変面白い。またJR大阪駅を利用するといつも感じる階段が多い理由もわかった。地元の大阪を「高低差」から知ることができた面白い本だった。2017/03/15
Shoji
72
大阪の街が好きで、歴史や文化に興味があって、街歩きが好きな方にとっては面白い一冊だと思います。上町台地、大坂の町に巡らされた堀川、住吉湊や堺の地形と歴史など、大阪の郷土史にしばしば登場します。つまり、地理や郷土史が好きな人にとっては、新しくもないことが書かれています。でも、おかしなもので、知ってる事柄にも関わらず、この本はあきれることもなく、にやにやしながら読まれることでしょう。2017/04/23
よこたん
50
生まれ育った地域のことは、やっぱり好きだし、気になる。「縄文時代の大阪は海の底だった」やたらと坂の多い場所や、〇〇島という地名があちこちにあったりと、地形や地名で何で?とかねがね感じていた疑問が少し解消できた。上町台地は洪水がきても浸からないと、そのエリアに住む子に自慢?されたこと、壮大な大和川付け替え工事(江戸時代)の歴史を習ったのは、超地域限定(郷土の歴史)だったと後に知って、何だかションボリしたことを思い出す。中甚兵衛さん、私の中では偉人! 今も、まだまだゆっくりと地形は変わっているはず。2017/07/01
ねね
17
ほうほう、成る程。自分が足を運んだことのある場所だとより分かりやすく楽しめるかな?興味深いのですが、最後に至るまでまあ本当に高低差の話ばかりで…正直、最後の方はダレてしまいました(汗)難波宮の話とかも混ぜてくれてるんですが、どうも魅力に欠ける書き方で(私にとっては)誰かとコラボしてその辺り含め、再編集して頂けたらもっと楽しめるかなあと思ったり。高低差や地形好きな方には、散策のお供にオススメかも。2017/05/07
loanmeadime
14
もう15年前になりますが、大阪七福神めぐりというのをやったことがあります。その出発点が三光神社で、真田丸の抜け穴が保存されているそうですが、その時は全く気づきませんでした。上町台地を横断して平地に降り、最後また四天王寺に戻るコースですが、本書にある知識があれば色々と楽しめたかもしれません。靭公園端の永代浜跡のクスノキの前とか、上町台地北端の急坂が階段になっている北大江公園の横とか、仕事で何べんも通っています。退職する前に読んでおけばよかった・・・2023/02/27
-

- 和書
- 大韓帝国の保護と併合