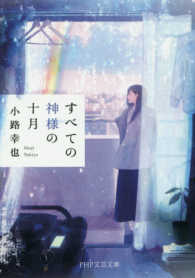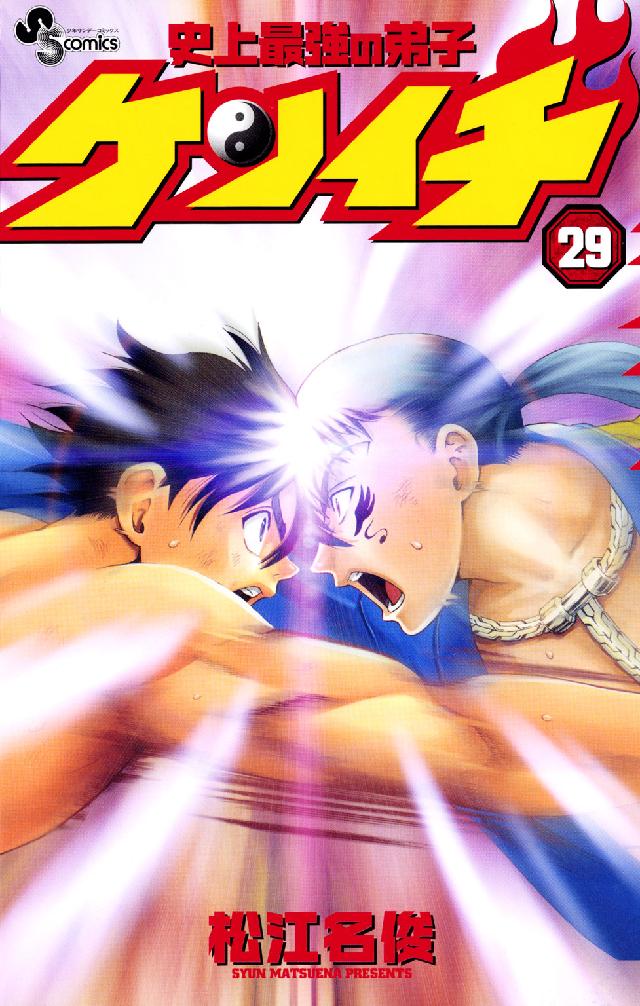内容説明
「伊勢えび」「真珠」「松阪牛」「伊勢神宮」などが連想されがちな三重県―。ヤマトタケル伝承や垂仁朝の伊勢神宮鎮座など、歴史は古くて多彩である。志摩の海女の歴史は古代に始まり、平安時代には伊勢平氏の基盤にもなった。伊賀地方に「忍術」が発祥し、県南では国司・北畠氏が地盤を築いていく。戦国時代には志摩の「九鬼水軍」が織田信長・豊臣秀吉のもとで活躍し、江戸時代に入ると小藩が分立し、県南は紀州藩領だった。明治に入ると創意にあふれた実業家や学者を輩出し、名産物を生み出してゆく。本書では、魅力あふれる意外な三重県の歴史を紹介する。
目次
第1章 三重県の古代(時代をよむ 「傍らのうまし国」は東西の接点だった;「伊勢国」の語源は神話上の人物「伊勢津彦」にちなむのか? ほか)
第2章 三重県の鎌倉・室町時代(時代をよむ 伊勢平氏と北畠氏の影響を強く受けた中世の三重;伊賀地方に「忍術」が発生したのはなぜ? ほか)
第3章 三重県の戦国時代(時代をよむ 国人・宗教勢力の割拠から織田信長支配へ;内外両宮門前の宇治と山田がたびたび抗争したのはなぜ? ほか)
第4章 三重県の江戸時代(時代をよむ 伊勢参りで賑わう街道、地域を越えて活躍した商人・文化人;桑名藩祖・本多忠勝が行った東海道宿駅整備と「七里渡し」の築港とは? ほか)
第5章 三重県の近代(時代をよむ 戦争と天災に苦しめられた三重県の近代;土方歳三のポートレートを撮った写真師・田本研造とは? ほか)
著者等紹介
山本博文[ヤマモトヒロフミ]
1957年、岡山県生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。文学博士。東京大学史料編纂所教授。専門は近世日本政治・外交史。『江戸お留守居役の日記』(読売新聞社、のち講談社学術文庫)で第40回日本エッセイストクラブ賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
hr
左近