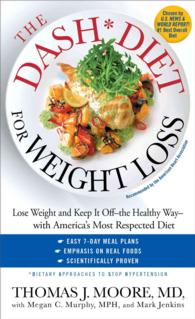内容説明
武装した百姓、郷村の地頭、傭兵たちが戦場の主役だった!伊達氏の「兵士動員記録」から、謎だった天下統一直前期の戦国軍団の構成員を解明。
目次
第1部 政宗の家臣団と「兵農分離」(奥州・伊達氏の出自と来歴;本拠地の変遷;伊達政宗の家臣団と実戦部隊;「兵士動員記録」と城のある風景)
第2部 政宗と百姓兵の合戦史(対大内戦―小名的存在の武将たち;対畠山戦―人取橋の激戦;対相馬戦―田村氏の後継者争い;対芦名戦―南奥州の覇権争い;奥羽仕置―耐え難い屈辱と執着;北の関ヶ原合戦―祖霊地奪還のチャンス;仙台城と人足徴用―城下町建設現場の風景)
著者等紹介
中田正光[ナカダマサミツ]
1946年三重県生まれ。青山学院大学文学部教育学科卒業。城郭研究家。特に、武田氏、北条氏の城郭研究で知られる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
maito/まいと
25
戦国時代後期からよく出て来る「兵農分離」。織田信長の天下取りの要因とされるこの事項は、実際どのような流れ(手順)で行われていたのか?歴史コアファンでも意外におざなりになりがちなこの話題が解説されている貴重な一冊。土地制度と管理者・納税者そして徴収者といったがんじがらめの納税制度が、君主が直接の雇い主になることで、領主階層の簡略化や直接管理を可能にした、という経緯はわかりやすく、兵農分離の実態を知ることができる。が、それ以外は政宗の半生と城を追うだけの安易な内容。タイトルから期待される内容は入っていない。2013/06/27
スー
18
48題名を見れば伊達家の部隊編成や戦術や鉄砲騎馬隊などの解説を期待してたけどあっさり裏切られる感じでした。内容ほ伊達家の歴史と政宗の戦史と戦国時代の農民達の置かれた状況の解説でした。農民は時に戦力として時に食料を生み出す資産として武士達に見られ味方なら守られ敵なら殺されたり売られたり食料を奪われる哀れな存在だという事がわかります。しかし彼等もただやられるだけではなく武装して幾つかの村や武士と協力して村や人を守っていた。しかし秀吉は士と農民を分け農民には食料生産に専念する事を命じるがやはり戦乱が起これば2022/06/08
ようはん
16
伊達氏の勢力範囲は地元なので聞き慣れた地名が多かった。実際に行った場所もあるが、ここに城跡があったのかという場所も多くいずれ足を運んでみたい。2022/09/24
Kiyoshi Utsugi
7
中田正光乃「伊達政宗の戦闘部隊 戦う百姓たちの合戦史」を読了しました。 先日、福島県にある桧原城、秋田県にある蘆名義勝の角館城(関ヶ原の戦いの後に移封されたところ)に行っていたので、気になって読んでみました。 摺上原の戦いをはじめとした伊達政宗が挑んだ戦いにどのように部隊を整えていったのかが書かれています。 摺上原が現在のどのあたりになるのかは、この本を読んで初めて知りました。 また桧原城、猪苗代城(亀ヶ城)は縄張図も書かれていたので、また改めて行ってみたくなりました。2019/12/08
鐵太郎
4
この本は、伊達家、すなわち戦国の独眼竜として名を馳せた伊達政宗の軍事組織を、その歴史、戦史の流れと共に描き、それによってこの時代の一大名の軍制の姿を示してくれました。この書き方、歴史の流れを一つの方向から描く手法の一つなのでしょうけど、なかなかユニークで面白いかも。とはいえこの本はどちらかというと、伊達政宗の生涯とか、彼の戦いの記録に重点があります。そして現代に残るその戦いにまつわる城や砦の遺跡とか。それはそれで面白いのですが、だとすると題名的にはどうなのかな。2013/08/11
-
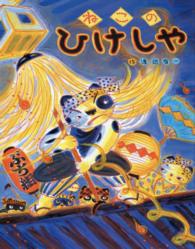
- 和書
- ねこのひけしや