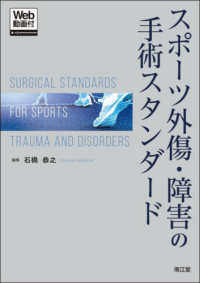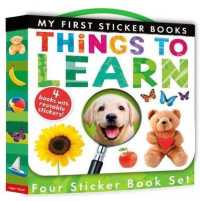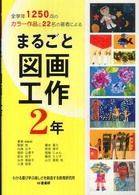内容説明
内閣府の調査によると「ひきこもり」層は70万人、予備軍も含めると225万人という膨大な数に上るという。しかし、その実態はなかなか伝わってこない。そして現在、ひきこもり層は「長期化」「高年齢化」し、ますますタブー化しているというのだ。時に家族を巻き込み、凄惨な事件に発展することもある「ひきこもり」問題。15年以上にわたりこの問題を取材してきた著者がレポートする、「ひきこもり」の知られざる現実と解決策。
目次
第1章 ひきこもり―家族の肖像(愛知県豊川市一家5人殺傷事件;「ひきこもり」の数は70万人 ほか)
第2章 “怠け”なのか“病気”なのか(緊張の糸がプツッと切れる瞬間;頂上に上ったら、転げ落ちていった ほか)
第3章 急増する「社会人ひきこもり」(新たな「ひきこもり」層の出現;「就労経験者はひきこもらない」という神話の崩壊 ほか)
第4章 路上にひきこもる人々(「ひきこもる」場所は関係ない;「ひきこもり」はセーフティーネットの枠外 ほか)
第5章 “ひきこもり社会”日本の処方箋(「非モテ」から「リア充」を目指す;なぜ自分は愛されないのか? ほか)
著者等紹介
池上正樹[イケガミマサキ]
1962年生まれ。大学卒業後、通信社などの勤務を経て、フリーのジャーナリストに。主に雑誌やネットメディアで「心」や「街」をテーマに執筆。1997年から日本の「ひきこもり」現象を追いかけ始める。「ひきこもり問題フューチャーセッション」などを通じて、当事者たちの新たな動きをサポートする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
カッパ
しょむ研(水野松太朗)†選挙マニア!?
キムチ
みい君
へっけ
-

- 和書
- 成長の生物学