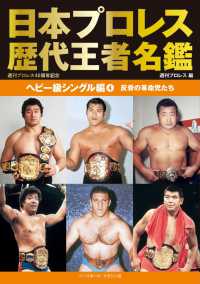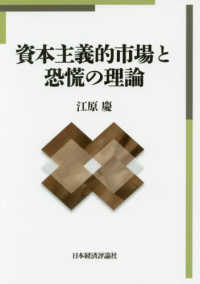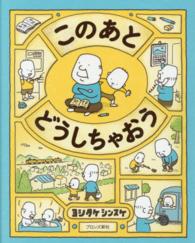内容説明
なぜ生き残る。路地裏“絶滅危惧種”の「娯楽力」と「癒し力」。
目次
第1章 昭和景色(闇市横丁(東京都豊島区池袋ほか)
コリアンタウン(東京都台東区東上野) ほか)
第2章 昭和の夜(ピンク映画;大人のおもちゃ屋(東京都渋谷区道玄坂) ほか)
第3章 昭和ゴーヂャス!!(旧車(埼玉県さいたま市)
ラジカセ(東京都足立区花畑) ほか)
第4章 昭和生活(寝台特急列車(東京都台東区・上野駅)
オートレストラン(埼玉県行田市) ほか)
第5章 昭和少年少女(ブリキ玩具(東京都墨田区)
野球盤(東京都台東区・エポック社) ほか)
著者等紹介
藤木TDC[フジキティーディーシー]
1962年生まれ。フリーライター。映画やAVの評論から、芸能史、横丁・小路の歴史探索、実話マンガ原作まで、雑誌を中心に幅広く執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
幹事検定1級
28
昭和の文化、産業、遊興を紹介する一冊。ディープな世界から懐かしい世界まで様々。特に懐かしさを感じたのはオートレストラン。あのホットサンドやうどん類には小中学生時代がよみがえるようです。この作品では埼玉の熊谷に存在しているということですが、現在もあるのでしょうか。ウェブで検索してみたいと思います。(図書館本)2018/03/13
風鈴
4
色々環境を変えたくて手に取りました。田舎出身の私には懐かしくもありまして。ちなみに鳥取の吉岡温泉町が地元です(笑)今は関西にいますけど。ラジカセとか、地方競馬やら角砂糖とか昭和のアイテムが目白押しです。平成も終わりますし、こういう本また出ないかな。2018/10/16
猫
2
昭和の時代に大きな存在感を植え付けたあれこれが、平成の世にいかに生き残っているかを紹介している。新しい技術、新しい価値観に取って代わられて消えていこうとする古き良き時代を、今も守ろうと頑張っている人がいる。ラジカセの修理を続けるために、メーカでは製造中止になった部品を個人で発注生産して修理にあたっている方の情熱に圧倒された。あと、角砂糖が市場から消えてきていることにこの本を読んで初めて気づいた。2015/02/27
ybhkr
1
一年くらい前にゴールデン街デビューしたばかりなので、あまり昭和ってかんじはしないかなあ。おめんやソフビも進化はしても続いているかんじ。ブロマイドなんかも生写真に形を変えてこのネット時代を生き延びている。ラジカセ、真空管アンプ、8ミリ映画あたりは本当に昭和。まったく違うツールにとってかわられたイメージ。今の子供たちにとってラジカセって蓄音機とかそんなレベルなのかなあ?そこまででもないか…。へび料理!まむしとか?うちのおとんが買ってきてたの思い出した…。花やしきはまだまだ現役でっせ~!2016/01/21
くたびれ役人
1
1項目4ページとコンパクトながらカラー写真が多く、文章もわかりやすくて面白かったです。個人的によかったのは、ラジカセ、8ミリ映画でした。メーカーが生産していない部品を個人で作ってしまう情熱には感心しました。赤本の古本が高値だという事実には驚きました。続編に期待します。2013/01/13