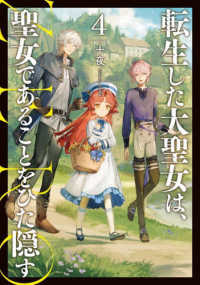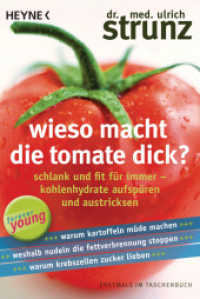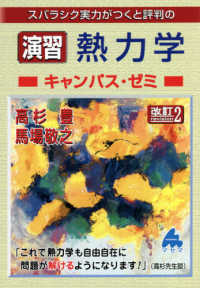- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > 学習
- > 文明・文化・歴史・宗教
内容説明
ユネスコ無形文化遺産に登録され、世界にみとめられた日本の「和食」。食材や料理としてだけでなく、文化としての「和食」の特徴やよさや歴史を、豊富な写真と図版でわかりやすく解説。「食」の循環の視点・視野を持って生活に和食をとりいれ、健康で楽しい、和食を基本とした生活を提案している。来日するイギリス人家族を和食でもてなすにあたり、自分たちが「和食」について何も知らないことに気づき、「和食」について改めて学ぶ。実際にイギリス人家族をもてなすのに、どのような食事づくりをすればよいか料理選択もふくめて実践する内容。全国の郷土料理マップや、行事食、給食の歴史など、巻末の資料集も充実。1冊丸ごと「子ども和食百科」。
目次
1章 日本文化と和食(和食はどのように生まれたか?;季節の行事や祭りと和食;地域性をいかした和食―郷土料理)
2章 和食の料理の成りたち(献立は、一汁三菜が基本;和食を支える日本の食材;和食のおいしさを引きだす調味料;保存が育ててきた和食;和食の調理法;和食の食器と食具)
3章 世界に広がる和食の魅力―和食でおもてなしをしたい!(どんなおもてなしにしようか?;なぜ、和食が世界から注目されているか;“和食でおもてなし”の基本方針を決める;料理を選んで、食事を設計する;「和食でおもてなし3・1・2」の食事づくり;直前の準備と役割分担;いよいよ、本番!)
資料集
著者等紹介
足立己幸[アダチミユキ]
女子栄養大学名誉教授・名古屋学芸大学名誉教授。保健学博士、管理栄養士。専門は、食生態学、食教育学、国際栄養学。現在、NPO法人食生態学実践フォーラム理事長、名古屋学芸大学健康・栄養研究所参与。東北大学農学部卒業。東京都衛生局技師等を経て、女子栄養大学へ。同大学・大学院教授を経て、2006年より名誉教授。2006年より名古屋学芸大学大学院教授、2011年より同大学健康・栄養研究所長、2014年より名誉教授。この間、ロンドン大学人間栄養学部客員教授、カーテン工科大学公衆衛生学部客員教授等として、発展途上国での食生態学研究や保健・栄養プログラム関係者への教育にも携わる
江原絢子[エハラアヤコ]
東京家政学院大学名誉教授・客員教授。博士(教育学)。専門は、食文化史、食教育史、調理学。お茶の水女子大学家政学部食物学科卒業。東京家政学院大学教授を経て、同大学名誉教授・客員教授。一般社団法人和食文化国民会議(略称:「和食会議」)の副会長として、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の保護・継承の活動を行っている
針谷順子[ハリガイヨリコ]
高知大学名誉教授。博士(栄養学)、栄養士。専門は、調理教育学、食生態学、栄養学。現在、社会福祉法人健友会・地域事業部部長。NPO法人食生態学実践フォーラム副理事長。女子栄養大学栄養学部卒業。高知大学教授を経て、2009年より同大学名誉教授。「食事バランスガイド」を策定した「フードガイド(仮称)検討会」委員及びワーキング部会委員等を歴任。2002年、「弁当箱ダイエット法」の研究で、日本栄養改善学会賞を受賞
高増雅子[タカマスマサコ]
日本女子大学家政学部教授。博士(栄養学)、管理栄養士。専門は、食生態学、調理学、家庭科教育。農林水産省食育推進委員、農林物資規格調査会委員などを歴任。日常生活における食のあり方、食を通しての社会システムのあり方、食生活の豊かさとは何かを研究。ラオス等発展途上国での学校給食プログラムや栄養指導にも携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。