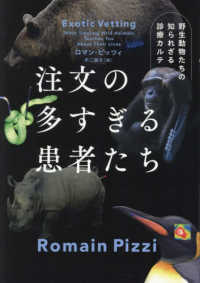内容説明
同じ授業を受けていて、差がついてしまう理由は、何なのでしょうか?4500人以上の生徒を直接指導し、周囲の東大生にヒアリングした結果、次のことに気づきました。「できる子は、勉強時間以外も学んでいる」では、どうすればそうなれるのか?その方法の1つとして、「10のマジックワード」を紹介します。10の「問いかける」言葉の力で、どんな親でも簡単に頭脳のスペックを引き上げることができるのです。
目次
第1章 同じ環境・条件なのに、なぜ“できる人”と“できない人”に分かれるのか
第2章 「学び」の3つのタイプとは?
第3章 できる人は「頭のつくり」が違うのか?
第4章 「意味が理解できる人」と「意味が理解できない人」の決定的な違い
第5章 OSをバージョンアップするアプローチ1「疑問を持たせる」
第6章 OSをバージョンアップするアプローチ2「まとめさせる」
第7章 さらにOSを強化する5つのマジックワード
著者等紹介
石田勝紀[イシダカツノリ]
一般社団法人教育デザインラボ代表理事。1968年横浜生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とある内科医
19
勉強本の続き。タイトル買い。自分がまだ変われるかどうかはさておき、医学教育にどう生かすかを考えながら読んだ。「同じ症例を経験していて、なぜ臨床能力に差がつくのか?」は常々現場で感じてきた課題。2024/11/04
masa
6
本書は、「10のマジックワードを投げかけることで、『自分の頭で考える力』を引き上げることが可能。それを日常で行ってしまおう」という内容。日頃から意識付けを行い、特に、目的意識力や原因分析力を磨きたいと思った。2025/12/21
グレートウォール
4
「考える力」が養われているかどうかが、肝らしい。この手の本は日本や海外の研究をベースとして論じられることが多くあるが、本書は著者が関わった塾での子どもたちや、これまでの自身の体験をベースとして書いている。 常に考えることで、思考が深まるわけで、それが差につながるという理解だ。 一つ、共感できた箇所としては、人は問われることで考えるという点で、つまり、問われないと考えないのだ。 自分で考え続けないとな。2025/03/10
TM
3
昨今のエビデンスベースの内容とは異なり、経験ベースで語られる内容。 実践はしやすそうだし、やって損する内容ではないので、理屈はさておきやってみていい。 また、経験ベースで語られているが、エビデンスベースの書籍でも提案されているような内容でもあるので、それを実践しやすい形にしているとも言えるかもしれない。 ただ、そこまですごいことが書かれているわけではないので、値段に比して情報価値は低いと感じた。 2025/02/24
Riopapa
3
日頃からどれだけ学ぼうとしているかが大事。これを考えると、俺の勉強に対する姿勢は甘かった。教師として、親として、子供にどう考えさせるかも書いてある。まだ少し間に合うか。2024/10/06