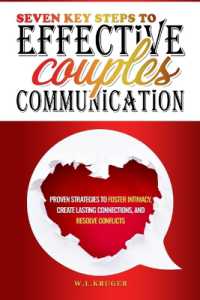内容説明
フェイクニュースや陰謀論が日常の中にふと紛れ込む、このカオスな社会。非科学的な情報に惑わされず、正しい判断をするために。自分で考える力が身につく1冊。
目次
第1章 科学にまつわる「思い込み」の罠―「科学的」って何?(科学的に正しいことは、100%正しい;科学の力は万能である;専門家が言うなら正しい)
第2章 あなたのまわりにひそむ「非科学的」思考―この情報、もしかして怪しい?(健康・美容の商品はトンデモ科学だらけ;非科学的思考が入り込みやすい「水」の話;理解の範囲を超えた科学技術との付き合い方;情報の受け取り方にも、科学リテラシーがあらわれる;データを正しく見る技術を身につける)
第3章 科学リテラシーを鍛える習慣―科学とどう付き合っていく?(そもそも、なぜ「科学リテラシー」が必要?;科学リテラシーが加速する「科学の基礎知識」;「科学的思考力」は日常の中で鍛えられる;科学リテラシーを鍛える読書術;科学リテラシーはクリエイティビティの土台にもなる)
著者等紹介
竹内薫[タケウチカオル]
猫好きサイエンス作家。東京大学教養学部教養学科、同理学部物理学科卒。カナダ・マギル大学博士課程修了(専攻は高エネルギー物理学)。理学博士(Ph.D.)。わかりやすい科学解説や科学評論に定評がある。NHK Eテレ「サイエンスZERO」の司会など、テレビ、ラジオでも活躍。YES International School校長。ZEN大学基幹教員に就任予定(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
南北
みき
Carlyuke
to boy
-
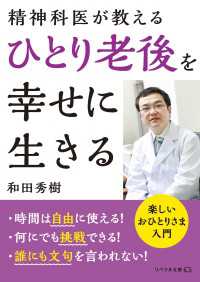
- 電子書籍
- 精神科医が教える ひとり老後を幸せに生…
-
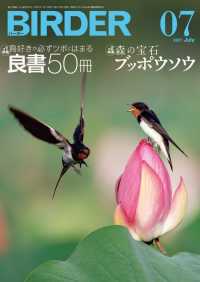
- 電子書籍
- BIRDER2021年7月号