内容説明
対話型組織開発、教育、心理療法etc.注目を集める「社会構成主義」最良の入門書。ここに対立を超える鍵がある―。
目次
第1章 「社会構成」というドラマ(「私たちが世界を創造している」という基本的な考え方;「言語ゲーム」から「可能性のある世界」へ ほか)
第2章 「批判」から「再・構成」へ(「脱・構成」とそれを超えて;「個人」から「関係」へ ほか)
第3章 社会構成主義と専門行為(社会構成主義と心理療法の変化;社会構成主義と組織の有効性 ほか)
第4章 社会構成主義の実践としてのリサーチ(知識という行為を「再・構成」する;社会調査の方法の開花)
第5章 「批判」から「コラボレーション(連携)」へ(「ニヒリズム」から「豊かな現実」へ;「現実主義」を超えて:体、心、力(権力) ほか)
著者等紹介
ガーゲン,ケネス・J.[ガーゲン,ケネスJ.] [Gergen,Kenneth J.]
スワースモア大学心理学教授およびタオス・インスティテュート(Taos Institute)所長
ガーゲン,メアリー[ガーゲン,メアリー] [Gergen,Mary]
ペンシルベニア州立大学心理学教授および女性学教授。タオス・インスティテュートの創立メンバーでもある
伊藤守[イトウマモル]
株式会社コーチ・エィファウンダー。日本人として初めて国際コーチ連盟(ICF)よりマスター認定を受ける。「コーチング」を日本に紹介し、日本で最初のコーチ養成プログラムを開始。エグゼクティブ・コーチング・ファームである株式会社コーチ・エィを設立し、企業のリーダー開発や組織風土改革に携わる
二宮美樹[ニノミヤミキ]
フランス・パリ大学ドフィーヌ校国際ビジネス修士号取得。コーチ・エィにてグローバル情報調査を任される(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koichiro Minematsu
きいち
羊山羊
りょうみや
江口 浩平@教育委員会
-
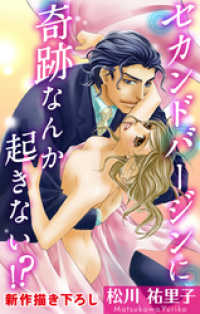
- 電子書籍
- Love Silky セカンドバージン…








