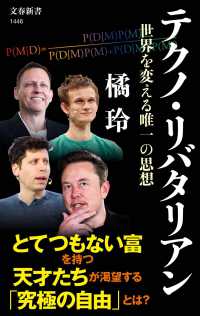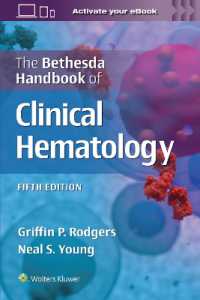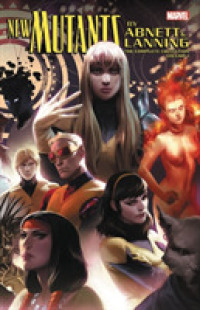内容説明
誰もがみな本能的に失敗を遠ざける。だからこそ、失敗から積極的に学ぶごくわずかな人と組織だけが「究極のパフォーマンス」を発揮できるのだ。オックスフォード大を首席で卒業した異才のジャーナリストが、医療業界、航空業界、グローバル企業、プロスポーツチームなど、あらゆる業界を横断し、失敗の構造を解き明かす!
目次
第1章 失敗のマネジメント
第2章 人はウソを隠すのではなく信じ込む
第3章 「単純化の罠」から脱出せよ
第4章 難問はまず切り刻め
第5章 「犯人探し」バイアスとの闘い
第6章 究極の成果をもたらすマインドセット
終章 失敗と人類の進化
著者等紹介
サイド,マシュー[サイド,マシュー] [Syed,Matthew]
1970年生まれ。英『タイムズ』紙の第一級コラムニスト、ライター。オックスフォード大学哲学政治経済学部(PPE)を首席で卒業後、卓球選手として活躍し10年近くイングランド1位の座を守った。英国放送協会(BBC)『ニュースナイト』のほか、CNNインターナショナルやBBCワールドサービスでリポーターやコメンテーターなども務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
266
「我々は自分の失敗には言い訳をするくせに、人が間違いを犯すと直ぐに攻め立てる」という周知されている事実から、「なぜ成功者はほんの一握りなのか?」について次のように思索してみました。『自分の失敗を認めることが出来るヒトは一握り。そして、失敗を認めて改善出来るヒトはそのさらに一握り。つまり、成功者はほんの一握り』と説明できるんじゃね?、とwww。2024/01/17
けんとまん1007
265
とても多くの気づきのある1冊。失敗の定義は、いろいろあるし、いろいろな方の考え方も眼にすることがある。個人的には、羽生善治さんの定義が納得度が高い。そんな失敗から、何を学びどう活かすのか?さらに、この本の優れているのは、何故失敗が起きるのか?その判断に至るプロセスは正しいのか?何故、人は失敗を認めようとしないのか・・・などに触れられていることだ。それは、文化・歴史という影響もあるが、いい意味で、少しずつ変わっていかないとと思う。デザイン思考にも通じるものを感じた。2020/12/06
breguet4194q
182
失敗という誰もが避けたい事柄について、冷静に科学した一冊。言われてみれば、確かにそういう思考回路になっていると思う箇所が散見された。人命に関わる程の大事件が、身近で起こった事がないから真剣になれない自分でもある。失敗をどう捉えて、次に活かしていくか。自分の行動を見つめ直す事ができました。本当に読んで良かった。2020/05/17
kei-zu
150
本書読んでいる間、Amazonが実店舗を閉鎖するというニュースを見た。独自スマホの参入と素早い撤退など、同社のトライ・アンド・エラーには感心する。 本書で紹介されたエピソードのうちで面白かったのが、一流の技術者が対処できなかった部品の改善を、ダメもとで生物学者に行わせたら問題が解決したというもの。ポイントは、ちょっとずつの工夫の蓄積。できあがった部品は、当初の想定とは随分と異なった外見をしていたという。 本書に通底する「失敗の蓄積に勝る改善手段なし」という指摘には、大いに励まされる。2022/03/04
ひろき@巨人の肩
127
人間は本能的に失敗を遠ざける。だからこそ、失敗から積極的に学ぶ僅かな人と組織だけが「究極のパフォーマンス」を発揮する。多数の事例より失敗を構造化して、この要諦を導き出す名著。失敗を誘発する「時間感覚の麻痺」は「焦り」と「集中」により起こる。人はウソを隠すのではなく信じ込むことで、失敗を遠ざける。特に「恥ずかしさ」や「努力」は判断を鈍らせる。「自尊心」「イデオロギー」「物語」「犯人探し」はバイアスを生み失敗の学びを妨げる。成長には失敗が欠かせない。進化とは選択の繰り返し。すべえ失敗ありきで設計する。2022/05/01
-

- 電子書籍
- グランドジャンプめちゃ 2025年12…