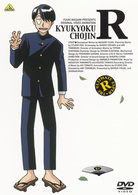内容説明
われわれの祖先はジャングルで暮らしていた時代から、環境に適応するためにさまざまな感情を身につけてきた。「恐怖」「怒り」「愛情」「嫉妬」「楽しさ」「幸福」等々、感情から人類進化の秘密が見える。
目次
「野生の心」と「文明の心」
恐怖と不安
怒りと罪悪感
愛情と友情
好きと嫌い
嫉妬と後悔
自己呈示欲と承認
楽しさと笑い
悲しみと希望
信奉と懐疑心
驚きと好奇心
名誉と道徳感
幸福と無力感
著者等紹介
石川幹人[イシカワマサト]
1959年東京生まれ。東京工業大学理学部卒業。同大学院物理情報工学専攻、企業および国家プロジェクトの研究所をへて、現在明治大学情報コミュニケーション学部教授。大学・大学院では、生物物理学・心理物理学を学び、企業では人工知能の開発に従事。遺伝子情報処理の研究で博士号(工学)を取得。専門は認知情報論および科学基礎論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うりぼう
50
竹内久美子さんのわがままな遺伝子の戦略的自己複製作戦を思い出す。進化ということは、心理学でも同じということか。肯定感情が集団を結束させ、チベットモンキーの下位の雄は、子どもをダシに使う。同情が悲しみの共有であり「野生の心」なら「お金」は「文明の心」であり、2つの両立は、心の葛藤を産む。感情も遺伝情報とすると、新しくつくることは時間がかかるが、失うのは容易で、廃用症候群と同じ。文明化するほど野生の幸福感が希薄になり「文明のこころ」での幸福感の確立が求められる。多様な自己と多様な集団が輻輳し、緩やかに繋がる。2011/07/31
Lee Dragon
23
自己呈示が複雑な自己の簡素化であると言う話が面白かった。しかし、一貫性を持ちたいと言うところから何となく心にわだかまりが出来てしまうと言う事もよくわかる。この悩みは普遍的なものであると思うので、悩んでいる人にしてあげたい。 また、バタイユの過剰と蕩尽の話も面白い、人の幸福を関数で表すと微分した時に正である、つまり直前の過去との比較によって成り立つのだと思った。これは神経の抑制系の鈍化の話をマクロに拡張したものと同じである。当てつけかもしれないがマクロの視点とマクロな視点の対応が見つけられて面白かった。2019/08/05
ヨミナガラ
22
“このところ、うつ病の患者が増えていますが、人々が無力感を冷徹に認知するようになったためかもしれません。人々はふつう、自己の力を過大視することで、無力さを直視しないようにしています。第8章で議論した「希望」をいだくのです。ところが、うつ病の患者は、より正確に自己の力を評定できる傾向が知られています。正直者が病気になってしまうのであれば、社会は欺まんに満ちているということです。それは深刻な問題です。”“個人におうじた多様な幸福を引き受ける理想のコミュニティには、集団の多層性が必要だと思われます。”2014/06/22
haruka
18
人間の感情はなぜこうも複雑に進化したのか。まず嫉妬は子孫を残すため。一夫一妻制は男女ともに実は利益があった。自己呈示欲求は集団への貢献を示すため。好奇心と勇気は危険だけど、数少ない成功者はモテて子孫を残せた。幸福感は衣食住を満たすため。衣食住に不足がない状態が続くと幸福感は意識にのぼらなくなり、やがて無力感が広がる。チンパンジーは人間と違って後悔も絶望もせず「今ここ」の世界を生きているらしい。仏教なんて教わらなくても彼らの方がよっぽど悟りに近い。悲観的でもなく単純に、もう人間には生まれ変わりたくないなぁ。2021/08/12
かりん
7
2:《狩猟採集生活にふさわしい感情で、現在を生きている。》積読本をざっと。そんな読み方のせいか、あまり残ったものがなかった。博愛の精神を持つのが難しいということと、長期的な食べすぎを抑制する遺伝情報が備わっていないということは、小ネタとしていただきました。2014/02/24
-
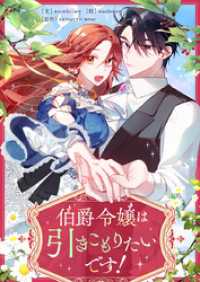
- 電子書籍
- 伯爵令嬢は引きこもりたいです!【タテヨ…
-

- 電子書籍
- 美人女上司滝沢さん【分冊版】 70 ド…