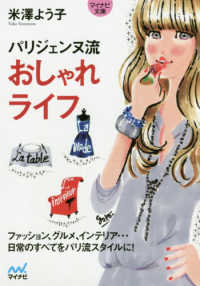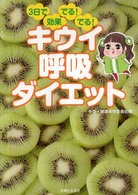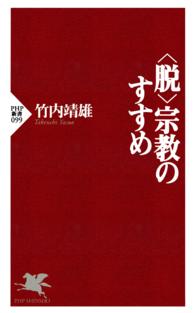出版社内容情報
日本的オープンな信仰のあり方の源流はどこか?ミルフィーユのような時代の層を、テレビでも活躍の著者が「横から目線」で解きほぐす。
内容説明
史実の裏にはいつも「信仰の力」がうごめいている。宗教の問題を真正面からとらえ直すことで、通説を覆す新たな人物像や意外な側面が見えてくる。現役カリスマ教師が教える教養としての日本史講座。
目次
はじめに 歴史の重なりを“横から”見てみると…
1 縄文時代から古墳時代(信仰のこころが芽生えた時代)
2 飛鳥時代(新たな外来宗教と向き合った時代)
3 奈良時代(国をあげて神仏の並存が模索された時代)
4 平安時代(とても平安などとはいえなかった時代)
5 鎌倉時代(現代人が最も振り返るべき時代?)
6 室町時代(信仰が生活と一体になっていた時代)
7 安土・桃山時代(日本の文化が神仏から解き放たれた時代)
8 江戸時代(宗教が権力に干渉された時代)
9 明治・大正・昭和時代(宗教と権力の関係が大きく揺らいだ時代)
終章 そして「なんでもあり」へ―寛容と受容の日本文化
著者等紹介
浮世博史[ウキヨヒロシ]
奈良県北葛城郡河合町の私立西大和学園中学校・高等学校社会科教諭。難関中学に合格者を輩出する進学塾浜学園にて社会科主管・教育研究室主管、同じく進学塾希学園にて社会科主管を歴任し、塾講師として二十年近く中学受験・高校受験の指導にあたる。その後、大阪市天王寺区の私立四天王寺中学校・高等学校社会科主任をへて現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
蓮華
Aby
Yoshihiro Yamamoto
omake
たかひー