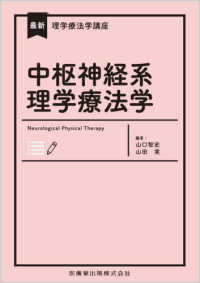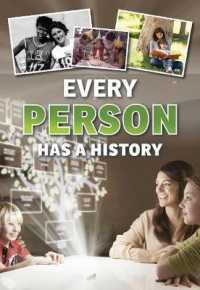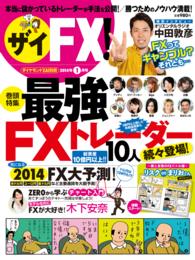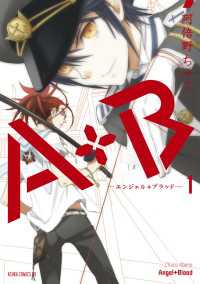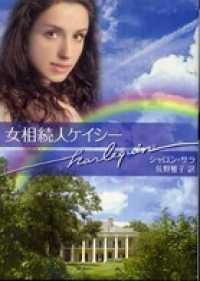内容説明
六〇年代頃のマンガブーム以降、多くの人々に享受されるようになり、今や日本の大衆文化の代表格となったマンガ。その多岐にわたる題材は、その時々の社会情勢や人々の心理を常に映し出しだす鏡でもあった―。少年/少女/青年/成人あらゆるジャンルのマンガに精通し、日本文化としてのマンガの特性を深く追究した著者による、七〇~八〇年代当時としてはきわめて前衛的な論考を収録。社会学者としてのマンガ文化社会論に、マンガ愛好家としてのマンガ作品・作家解説も加わった、これまでの作品集バックナンバーとはまた一風変わった一冊。
目次
1 マンガ文化(マンガ・メディア論;少年マンガ小史;青年文化としてのマンガ文化;劇画表現の構造と論理;原作者小論;劇画の変貌―「巨人の星」と「あぶさん」のあいだ;いい女たちの肖像;少女マンガ管見―一九七七年;成人女性コミックスの成立;コミック表現における「私」と「地域」;タフな被疎外者の肖像;子どもとマンガ―「ドラえもん」人気をめぐって;断章I;断章II)
2 現代マンガ論(パロディについて―東海林さだお「新漫画文学全集」;現代日本におけるホワイト・カラーの状態―福地泡介「ドタコン」「ドボン氏」;地平線からの呼び声―園山俊二「ギャートルズ」;日常生活の思想―長谷川町子「サザエさん」;好色・ナンセンス・反権力―黒鉄ヒロシ小論;政治マンガの第三の領域―はらたいら「ゲバゲバ時評」など;追跡譚―篠原とおる「さそり」、さいとう・たかを「ゴルゴ13」;父親について―古谷三敏「ダメおやじ」、小池一雄・小島剛タ「子連れ狼」;男と女―上村一夫「狂人関係」;三つのエッセイ―つげ義春の世界(拒否と孤独―つげ義春論・序説、現代の貧しい生―「ねじ式」、仮面の思想―「ゲンセンカン主人」)
憎悪について―楳図かずお「おろち」
劣等感と自尊心―「赤い靴」と「ゲゲゲの鬼太郎」
巨人伝説の崩壊と再建―われらの怪獣はどこにゆくのか
附章 マンガ文化の社会学的考察)
3 遊びの社会学(少年マンガにおける想像力の問題―楳図かずお「漂流教室」を素材として;「ゴルゴ13」はどう制作されているか―さいとう・プロダクション小論;少年マンガの魅力―ひとりの愛好者の微視的感想)