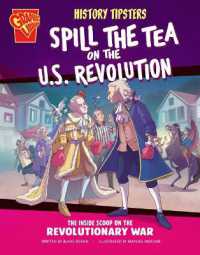内容説明
学生間の「協働的な学習」が教育に求められるようになって久しいが、その本質的意味を吟味せず無批判に授業形式だけを享受しても、それは名ばかりのものとなってしまうだろう。本書は、同一視されがちな「協同学習」や「協調学習」と明確に区分し、それぞれの教育理論家・実践家の系譜を丁寧に辿ることで、20世紀の米国で培われた「協働的な学習」のルーツを明らかにする。教育諸分野にかかわる研究者のみならず、現場の小・中・高・大学の教員の授業実践にも核心を与える挑戦作である。
目次
第1部 協同学習の成立・展開過程―知識・スキルの習得を保障する方法の探究(協同学習と進歩主義教育の関係;D.W.ジョンソンによる協同学習の定式化;協同学習研究の広がりと技法開発のアプローチ;R.E.スレイヴィンの協同学習と学校改革)
第2部 協調学習の成立・展開過程―共同体における「文化」への参加と創造(K.A.ブラフィーによる文化再変容としての協調学習;文化―歴史理論の拡張と「協調」の追求;認知的徒弟制における協調学習の役割;G.スタールによる「グループ認知」理論)
著者等紹介
福嶋祐貴[フクシマユウキ]
1990年京都府南丹市生まれ。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。2018年より盛岡大学文学部児童教育学科助教。専攻は教育方法学(学習形態論、教育評価論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 整形夫婦─アンチエイジング─(分冊版)…