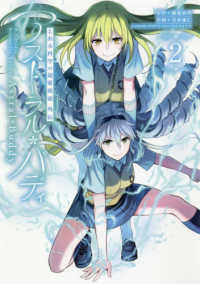内容説明
21世紀の今日における社会科の授業は、学校ごとの環境要因の変化や、さまざまな言語的・文化的背景を持った生徒の増加など、目まぐるしく変容していく新たな時代への対応を常に考えなければならない状況にある。そのためには、教育研究者―理論と教員―実践の双方を包摂した「共同体」の中で授業のあり方を構築していくことが急務だ。本書は、研究者と教師の協働・対話により社会科授業をめぐる理論と実践を総合することで時宜に適った「社会科授業」を創造する方法論を明示した、研究者・教員必読の一冊である。
目次
社会科授業研究の意味と方法を問い直す―本書の目的と方法
第1部 パースペクティブ―社会科授業研究方法論をめぐる争点(社会科授業研究方法論の展開と課題―客観主義と構成主義の相克を超えて;協働・対話という視点によって授業の何が見えるか?―論理実証アプローチと社会文化的アプローチ)
第2部 ケーススタディ1―共同体の授業研究から教師の成長を見通す(協働・対話による中学校社会科授業研究のプロセスを描く;協働・対話による小学校社会科授業研究のプロセスを描く)
第3部 ケーススタディ2―教師の実践から共同体の授業研究の役割を見通す(教師の経験から生まれる社会科教育観と授業研究スタイル―個別教師のライフストーリーから見る、理論と教育観の相互補完性と共同体;多様な教育観を持つ教師によって創り出される授業―アメラジアンスクール・イン・オキナワでの実践から)
第4部 アプローチ―共同体・対話・教師の視点から描く授業研究の可能性(子どもの発達データを用いて論理実証アプローチを再構築する試み―中学生の批判的思考力の発達を促進する歴史授業デザインを通して;社会文化的アプローチで日本の社会科研究を変革する試み;学び合い発展する実践研究共同体をつくる―産学共同によるプロジェクト型日本語教育実践)
第5部 パースペクティブ、再び―共同体・対話・教師から見る授業研究の未来(協働・対話による社会科授業の創造と授業力の形成―社会科授業研究方法論の再構築)
著者等紹介
梅津正美[ウメズマサミ]
鳴門教育大学大学院学校教育研究科教授。博士(教育学)(広島大学)。島根県生まれ。広島大学大学院教育学研究科教科教育学専攻博士課程前期修了。島根県立高等学校教諭、広島大学附属福山中・高等学校教諭、鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授を経て、現職。主な研究領域は、社会科授業構成論、米国の歴史カリキュラム編成論など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
杉さん
-
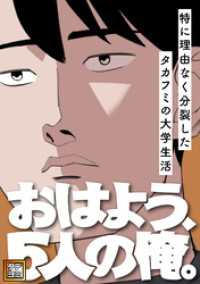
- 電子書籍
- おはよう、5人の俺。~特に理由なく分裂…
-
![イジめてごっこ。[ばら売り]第36話[黒蜜] 黒蜜](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1727890.jpg)
- 電子書籍
- イジめてごっこ。[ばら売り]第36話[…