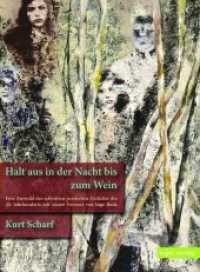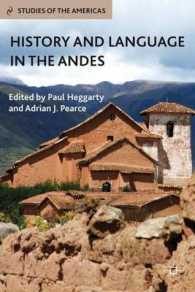- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
私たちが悲しむとき、悲愛の扉が開き、亡き人が訪れる。死者は私たちに寄り添い、常に私たちの魂を見つめている。悲しみは死者が近づく合図なのだ。大切な人をなくした若い人へのメッセージを含む、渾身のエセー。
本書を書きながら、片時も離れなかったのは、何者かに用いられている実感である。
確かに文字を刻むのは私だが、言葉は自分の内心とは異なるところから生まれていることが、はっきりと感じられていた。(「あとがき」より)
〈1〉
悲しむ生者と寄り添う死者
悲愛の扉をひらく
協同する不可視な「隣人」―大震災と「生ける死者」―
〈2〉
1 死者に思われて生きる
2 コトバとココロ
3 没後に出会うということ
4 冥府の青
5 先祖になる
6 悲嘆する仏教者
7 死者の哲学の誕生
〈3〉
「うつわ」としての私―いま、『生きがいについて』を読む―
魂にふれる
あとがき
【編集者からのコメント】
大切な人を亡くした若者へ語りかける手紙のように書かれた「悲愛の扉を開く」、ご自身の奥様を看取った経験から実感した「魂にふれる」の各章は、誰もが胸を打たれることでしょう。
また、再評価の機運が高まる上原專祿の死者論について、神谷美恵子や池田晶子の著作の読みを深める言及など後世に残る作品です。
【著者紹介】
[著者]若松 英輔(ワカマツ エイスケ)
1968年生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。批評家。(株)シナジーカンパニージャパン代表取締役。「越知保夫とその時代」で第14回三田文学新人賞受賞。その後『三田文学』に「小林秀雄と井筒俊彦」、「須賀敦子の足跡」などを発表し、2010年より「吉満義彦」を連載。また『小林秀雄――越知保夫全作品』(慶應義塾大学出版会、2010)を編集。著書『井筒俊彦 叡知の哲学』(慶應義塾大学出版会、2011)、『神秘の夜の旅』が大きな話題を呼ぶ。
内容説明
私たちが悲しむとき、悲愛の扉が開き、亡き人が訪れる。―死者は私たちに寄り添い、常に私たちの魂を見つめている。私たちが見失ったときでさえ、それを見つめつづけている。悲しみは、死者が近づく合図なのだ。―死者と協同し、共に今を生きるために。
目次
悲しむ生者と寄り添う死者
悲愛の扉を開く
協同する不可視な「隣人」―大震災と「生ける死者」
死者と生きる(死者に思われて生きる;コトバとココロ;没後に出会うということ;冥府の青;先祖になる;悲嘆する仏教者;死者の哲学の誕生)
「うつわ」としての私―いま、『生きがいについて』を読む
魂にふれる
著者等紹介
若松英輔[ワカマツエイスケ]
1968年生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。批評家。(株)シナジーカンパニージャパン代表取締役。「越知保夫とその時代」で第14回三田文学新人賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アルピニア
オカピー
nbhd
eirianda
なおみ703♪
-

- 電子書籍
- Pinocchio 【English/…