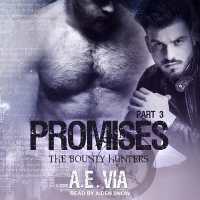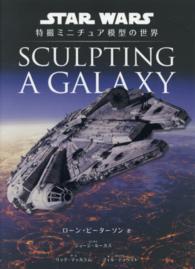出版社内容情報
オキシトシン、ドーパミン、セロトニン etc. 人材育成やチーム力の向上はいつの時代も重要なトピックです。しかし、「メンバーや部下がなかなか育たない」「チームの結束力が生まれない」といった悩みはありませんか?数々のチームビルディング手法や理論を試してみても、なぜかうまくいかないのならそのやり方に問題があるのかもしれません。実は、生命科学の理論を知れば、チームビルディングや人材育成の問題を解決することができるのです。本書では、生命科学の理論とともに従来の課題からいま注目される手法まで、30のテーマを解説しています。ヒトの原理・原則を根元から理解して、効果的なチーム作りを目指しましょう。 Introduction これだけは知っておきたい生命科学の知識(脳・神経の重要知識;ホルモンの重要知識;遺伝子の重要知識) 鈴木泰平[スズキタイヘイ]
はたらきがいは、ホルモンがつくる。
いつの時代も人材育成やチーム力の向上はホットなトピックです。
しかし、新しいチームビルディング手法や理論を試してみても、
なかなかうまくいかないという経験はありませんか?
「コーチングをしているのにうまくいかない」
「何をやってもチームがまとまらない」
「サーベイを実施してもエンゲージメントが上がらない」
このようなフレーズに心当たりのある方は、
やり方がまちがっているのかもしれません。
実は、生命科学の理論を知れば、なぜうまくいかない
のかを理解し、問題を解決することができるのです。
人材育成の原理・原則を根元から理解して、
効果的なチーム作りを目指しましょう。
【こんな人におすすめ】
・組織・チーム作りに携わる方。中でも、部下の育成に悩みを抱えている方。
・中小企業の経営者、人事の方。スタートアップの経営者など。
【著者紹介】
鈴木泰平(株式会社ワークハピネス)
理系大学で分子生物学やタンパク質工学、エピジェネティクスなど生命科学を幅広く学ぶ。
「研究者になりたい」という志を持って入学したが、研究室の風土が合わず挫折を経験する。
「人は場の雰囲気や風土に大きく影響される」ということを強く実感し、組織開発に興味を持つ。
自身のバックボーンである生命科学のナレッジを生かした人材育成・組織開発の手法を
開発、提供をする。自身の探求テーマは「生命の原理原則に
基づいた人材育成」「場に命を与える組織開発」
【目次】
Introduction これだけは知っておきたい生命科学の知識
Part 1 関係性を築く
Chapter 1 信頼を高める
Chapter 2 共感を高める
Chapter 3 協力を強める
Part 2 エネルギーを生み出す
Chapter 4 モチベーション(やる気)を引き出す
Chapter 5 生産性を高める
Chapter 6 回復力を高める
Part 3 イノベーションを起こす
Chapter 7 思い込みを外す
Chapter 8 創造性を発揮する 内容説明
目次
1 関係性を築く(信頼を高める;共感を高める;協力を強める)
2 エネルギーを生み出す(モチベーション(やる気)を引き出す
生産性を高める
回復力を高める)
3 イノベーションを起こす(思い込みを外す;創造性を発揮する;シナジーを起こす)
4 健康的でナチュラルな組織づくり(生命から学ぶ組織の作り方)著者等紹介
東京理科大学基礎工学部生物工学科卒。大学で分子生物学やタンパク質工学、エピジェネティックスなど生命科学を幅広く学ぶ。「研究者になりたい」という志を持って入学したが、研究室の風土が合わず挫折を経験する。また大学アメフト部での活動の中、チームの雰囲気の良さによって個人のパフォーマンスやチームのモメンタム(勢いや流れ)が大きく変わることを体感。「人は場の雰囲気や風土に大きく影響される」ということを強く実感し、組織開発に興味を持つ。その後ワークハピネスに参画。自身のバックボーンである生命科学のナレッジを生かした人材育成・組織開発の手法を開発、提供をする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
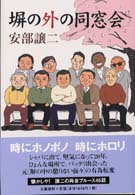
- 和書
- 塀の外の同窓会