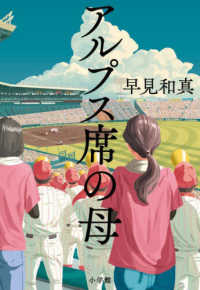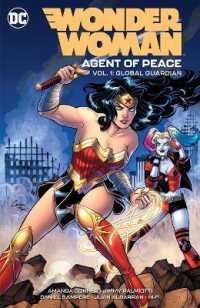内容説明
まったくあたらしい、組込み技術者のための教科書が誕生しました。組込みエンジニア教科書は、エンジニアの手によって著されたエンジニアのための教科書です。本書は、要件定義/分析/設計からソースコード作成に至るまでの工程で、構造化手法に基く組込みソフトウェア開発について解説します。ソフトウェア開発の基本である構造化手法を、モデリングを行うことで今日的なソフトウェア開発手法として身に着けることができます。
目次
1 はじめに
2 課題説明
3 失敗事例
4 要求モデリング
5 分析モデリング
6 設計モデリング
7 プログラミング
8 設計品質
9 レビュー
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
20
うまく構造化できるということは、うまくモデルが作れたというのと同義だと思っていました。そのため、要求分析、設計、ソースコード作成は一体として構造化へまっしぐらだという感じです。対象となるシステムによって、構造化の仕方が違うかもしれません。経験が豊富ではないので、本書も一つの事例として参考にさせていただきます。ありがとうございます。 愛知県立名古屋高等専門校の教科書として購入。内容を精査すると、特定の開発分野の事象を一般的に述べているところがあり要注意。二社間取引と市場出荷の場合の違いを触れてないのは残念。2026/02/05
たいそ
6
2006年。ついつい「モジュールの仕様はソースコードを見てください」に流れがちなので「設計と実装を同期させよう」を心掛けたい。NTCR条件、請願されないイベント、7±2の理論、最大抽象点、凝集度(コヒージョン)、結合度(カップリング)、ファンイン/アウトという用語を知ることができた。モデリングツールである「イベントリスト」「DFD」「構造図」を実践で使えるようにしたい。「設計とはシステムとして何を提供するのかであって、どのように動かすかではない。」2019/08/18
yuji
5
2006年の本。オブジェクト指向開発を勉強していた頃に読んだ本。分析モデリングとしてDFD、デシジョンツリー、状態遷移図を使って処理の見える化、組込み系なので業務フローはでてこない。構造化を行っている。設計品質については、凝集度、結合度の話も出てくる。もう読まないので処分。2025/07/19
明るいくよくよ人
1
構造化分析・設計手法による沸騰ポットの要求・分析・設計モデル化について記載。実務家がWorkshop形式で検討した実例が掲載されているものと思われる。実務的な見地からのモデル化の方法についての記載は有用。ただし、モデル間の一貫性に欠けるる点と誤植がややマイナス評価。2020/06/30
Kazuyuki Koishikawa
1
セサミってこれか2016/01/17