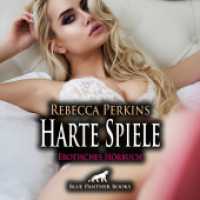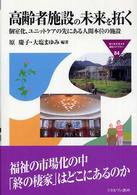出版社内容情報
マイクロカーネルOSは、「美しい設計ではあるものの、遅い実装」というイメージを持たれることがありますが、それは過去の話です。現在では、目立たないところで実用的なOSとして使われ、世界を支えています。
本書では、マイクロカーネルOSの概念からその実例まで、機能ごとに分けて説明しています。本書全体としては、基礎知識、マイクロカーネルの解説、その上で動くソフトウェア部分(ユーザーランド)の解説、そして発展的内容の4つのパートから構成されており、それぞれのパート内の章は、概念の解説部分と、その概念をどのように実装しているかを解説した実装部分に分かれています。
各章の実装例として、本書のために筆者が開発したマイクロカーネルOS「HinaOS」を用いて、わかりやすく解説しています。HinaOSは、エミュレータ上で動かすことを想定した教育目的のOSですが、OSの実装を学ぶのに必要となる最低限の機能を備え、ソースコードもシンプルにです。
また、HinaOSでの実装例のほかに、MINIX3、seL4、GNU Hurdという3つの実用マイクロカーネルOSによる実例も解説しています。複数のOSにういて紹介しているのは、それぞれに特徴があり、それを比較してほしいという理由からです。「マイクロカーネルOSとは、こういうものである」という固定観念を持たず、マイクロカーネルであるからこその柔軟さ、そして設計の自由さを味わってください。OSはコンピュータの使い方をガラッと変えられる、いわば新しいソフトウェアの世界を創れる土台なのです。
本書を読み終えたら、自分でOSを作ってみてください。OSの仕組みを理解していても、実装することで新たな発見があるものです。ゼロからOSを作るのではなく、HinaOSを拡張するのもよいでしょう。HinaOSには、実装が面倒な基本機能が既に備わっています。このようにOSを拡張しやすいのもマイクロカーネルの特徴の1つです。
本来、OSはとても自由なソフトウェアです。特定のCPUにしかない変わった機能を活用した移植性ゼロのOSを作るもよし、極限まで小さくしたOSを作るもよし、自由な発想で自分の世界を創り上げることができる最高の題材なのです。
本書を手に、マイクロカーネルの深淵をのぞき込んでみてください。その舞台裏を楽しんでいるうちに、OSやアーキテクチャにとらわれないコンピュータの深い技術も身に付いているはずです。
内容説明
OSはもっと自由だし、その舞台裏はずっと楽しい!自作OS(HinaOS)と実用OS(MINIX3、GNU Hurd、seL4)のソースコードを紐解き、ユニークなアイデアと先進的なテクニックを探究しよう!
目次
1 基礎知識(本書について;マイクロカーネル入門 ほか)
2 カーネル(プロセスとスレッド;メモリ管理 ほか)
3 ユーザーランド(ユーザーランド;API(Application Programming Interface) ほか)
4 発展的話題(マルチプロセッサ対応;仮想化とエミュレーション ほか)
Appendix 付録(HinaOS開発環境の構築;HinaOSのデバッグ ほか)
著者等紹介
怒田晟也[ヌタセイヤ]
筑波大学情報学群情報科学類卒業、筑波大学大学院リスク工学専攻修士課程修了。現在は、CDNにおけるエッジコンピューティング技術の開発に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ますみ
Q
walker
-

- 和書
- 部落解放研究 第142号