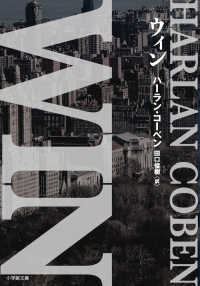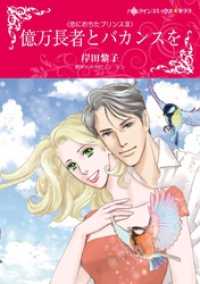出版社内容情報
千年の都は、ややこしいけど美しい。カリスマ案内人が京都の心を識ることができる「ツボ」を歴史や京都人の会話も交えて紹介。読めばたまらなく京都に行きたくなります。ガイドとしても使える一冊。
内容説明
カリスマ案内人にして生粋の京都人である著者が、京都の心を味わえる「ツボ」を紹介し、それらを愉しむことができる旅を提案。
目次
食のツボ(京の食;きつねとたぬき;京の水 ほか)
地のツボ(京の地;おひがしさん;鬼門の猿 ほか)
しきたりのツボ(京のしきたり;京の三大祭;祇園さん ほか)
著者等紹介
柏井壽[カシワイヒサシ]
1952年、京都府生まれ、京都府育ち。大阪歯科医大卒業。京都市内で歯科医院を営む。また旅や食にまつわる本を執筆。小説家としても活躍。また柏木圭一郎名義で京都を舞台にしたミステリーも多数執筆、好評を博している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
83
京都生まれ、京都育ちの著者が描く京の都の素顔。食のツボ、地のツボ、しきたりのツボに分けて書かれている。京都は観光地としてとても人気がある。いつも人出が絶えない。一方では京都の持つ独特の文化やしきたりがとっつきにくい人がいるのも事実、その類の本も出版されている。全てを否定することもなくその理由についてもわかりやすく説明している。きつねとたぬきうどん、おばんざいという料理、珈琲、柴漬け、東寺と西寺、一見さんおことわり、他読み物としても楽しい。京のぶぶ漬けについてなるほど~。観光に行かれる方も一読をお勧め。 2017/11/01
みっこ
56
【京都本】京都予習用。鴨川食堂の作者さんが書かれた本。京都が本当にお好きで、京都出身なことに誇りを持たれていることがわかる。食のところは特に参考になりました。生麩やたまごサンド食べてみたい!あとイノダコーヒにも行ってみたい。最後のしきたりのツボはなるほどなと。京都人は怖いとか冷たいとかいうイメージがあるけれど、遠回しな言い方を優しさと捉えると、印象が変わりますね。2018/08/13
里季
54
面白かった。以前読んだ「京都ぎらい」という本と違って語り口が柔らかい。私は滋賀県大津市出身だが、大津というところは不思議に京都に似ていて(真似してる?)面白い。言葉はほぼ京都弁だし、門はきの心得、曲がり角までお見送り、おもたせの習慣は誰に教わることなく親や近所のおばさま方に見習って育ったし、祇園祭に似ている大津祭りもある。お祭りには家で鯖寿司を作るし、冷えたちらし寿司は蒸し寿司にして食べた。道は同じように碁盤の目。ろぉじの面白さも。もうすぐ京都市民になる私。京都を勉強しよう。2018/03/26
Book & Travel
32
今度京都に行く機会があり、観光情報以外の知識も多少増やしておきたくて手に取った一冊。生粋の京都人の著者が真の京都文化を紹介したエッセイである。食べ歩きが増えた錦市場や、本来各家庭の味であったおばんざいを売りにしたお店など、古来からの美徳を逸脱したことに眉をひそめ皮肉る著者。他地域を少しディスりながら、京都は本来こうなのですと語るのは京都人らしいと感じつつ、成る程と思う内容も多い。他にもしば漬けと寂光院の繋がり、屋根瓦の鍾馗様のいわれ、京都の珈琲文化など様々な歴史を知ることができ、とても興味深く読んだ。2023/12/10
サルビア
27
生粋の京都人だからこそ説得力のあるお話でした。食のツボでは京の食について、地のツボでは京の地について、しきたりのツボでは京のしきたりについて書かれています。京都に住んで3年ですが、苦労しているのはおつきあいです。京のぶぶ漬けの中で「一事が万事、京都人はこんなふうな物言いをして、直截的な表現を避けます。遠回しに言ってみて、それでもうまく伝わらないときは、嘘も方便です。中略 こういうやり取りを嫌味だととらえる方もおられるでしょう。けれどもこれは、長い間、狭い都にひしめき合うように暮らしてきた人々が円滑に暮らし2020/09/05