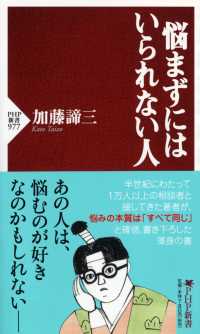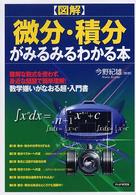出版社内容情報
『陰陽師』シリーズや『神々の山嶺』など、30年以上にわたり常に話題作を世に送り続ける作家が、これまでの作品を例に、着想のきっかけから情報収集、実際に「書く」技術まで、初めて公開します。
内容説明
ベストセラー作家であり続ける著者が、すべての創作に役立つ実践的技術を初公開。
目次
第1章 創作の現場―一つの小説ができるまで(三六五日、毎日書くということ;ある日、事故のようにテーマに遭遇する;ゴジラへの不満がキッカケとなる ほか)
第2章 創作の技術―面白い物語をつくるポイント(四歳からぼくは作家だった;文字のない時代にも物語はあった;「道」という漢字は「生首」に由来する ほか)
第3章 創作の継続―どうやれば続けられるか(二〇代―無心に書き続けた生活;三〇代―アイディアを“外”に求めることを知る;四〇代―死ぬまでにあと何冊書けるのか ほか)
著者等紹介
夢枕獏[ユメマクラバク]
小説家。1951年、神奈川県生まれ。東海大学文学部日本文学科卒業。77年、作家デビュー。89年、『上弦の月を喰べる獅子』(ハヤカワ文庫)で日本SF大賞、98年、『神々の山嶺』(集英社文庫)で柴田錬三郎賞、2011年、『大江戸釣客伝』(講談社文庫)で泉鏡花文学賞、舟橋聖一文学賞、吉川英治文学賞(2012年)などを受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コットン
60
既に文庫で読了済みだった。今回読み直してカード法とスケジュール管理に視線が向かった。2022/03/26
ぐうぐう
28
2014年にカルチャーセンターで語った講義をまとめた一冊。『「書く」技術』と題されているものの、文章における細かなテクニック論ではなく、書くための姿勢、作家としての心得、といった内容だ。けれど、それが抽象的な精神論になっていないのは、夢枕獏が培い、実践してきた方法論として語られていることによる、説得力に満ちているからだ。アイデアが枯渇し、考えても考えてもうまくいかないとき、どうすればいいか。夢枕獏は「とにかく書く」ことだと言う。(つづく)2018/02/04
ひさか
24
2015年1月刊。2014年4月〜6月の朝日カルチャーセンター新宿教室での3回の講義をもとに補講を加えまとめたもの。ということですが、聴いてみたい講義です。夢枕さん流の技術とそして心得が、興味深く語られています。大江戸恐竜伝の創作活動を例にしてあるのも面白かったです。アッという間に読了してしまいました。2015/04/23
冬木楼 fuyukirou
19
夢枕獏氏がどのように仕事(小説)に取り組んでいるかを語る。夢枕獏もたくさん書いているので、やはり小説家というのは「書く」「書き続ける」というのが仕事なんだと思った次第。 ところで、この本も先に読んだ森博嗣「小説家という職業」も図書館本なのだけど、分類が914エッセイでは無く901文学理論・作法の棚にあった。著者が好きで読破したい人には検索しないと見落とすような場所にある。逆にいえば、90*の棚では意外な作者の本が見つかったりするので、時々チェックをしている。2017/02/25
kubottar
15
やはりプロの仕事量はすごい。30代の頃の夢枕獏は月に原稿用紙平均500枚書いていたのは驚いた。やはりプロとアマの差というのは覚悟の違いなのだろうか?さて、書く技術という題名ですがハウツー的なことは一切なくエッセイ的な自伝となっていました。良い文章を沢山読んでたくさん自分で書く。シンプルなとてもストレートな技術でした。2017/07/29