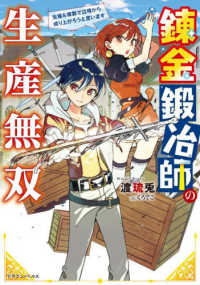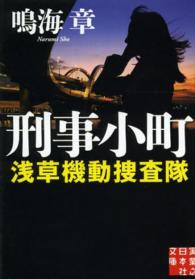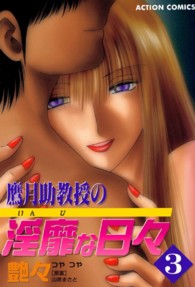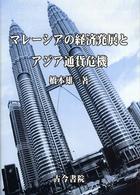出版社内容情報
★2016年セ・リーグ全員40代監督誕生。
いまプロ野球監督に求められる本当の資質とは何か?
球界の未来を危惧する前代未聞の監督論。
セ弱パ強、シーズン途中の監督解任、
オーナーの現場介入、選手兼任監督、
プレミア12準決勝敗退……。
問題や課題の多い今のプロ野球界に言えることは、
監督の人材不足である。
そもそも監督を育てるような環境が整っておらず、
負けが込むと安易に監督を変えるようでは、
いつまでたっても強いチーム作りは行えない。
このような「監督受難」の時代に
監督として必要な資質を、
勝負と人間の機微を熟知した
智将・野村克也が語る。
第1章 間違いだらけの侍ジャパン監督選び
第2章 12球団に本当の監督がいなくなった
第3章 私が仕えた4人の監督
第4章 監督に求められる資質
第5章 「期待できる人材は若手にはいない」という現実
本物の「プロ野球監督」がいなくなった――まえがきより
最近のプロ野球をみていて、とくに感じることは、
「とにかく勝てばいい」
「面白ければそれでいい」
という風潮が、以前にも増して顕著であるように思えて仕方がない。もちろん、プロ野球をビジネスとしてとらえた場合、一人でも多くのお客さんに球場に足を運んでもらうために、エンターテイメント性を高めることは必要なことかもしれない。しかし、それだけではプロ野球の本当の面白さを知ることができないのも、また事実である。
さらに言えば、野球中継がテレビの地上波からほとんどといってよいほどなくなってしまった。今年はセ・リーグが、シーズン終盤まで激しい首位争いを繰り広げ、またクライマックスシリーズも盛り上がっていたにもかかわらず、試合結果をニュースのスポーツコーナーで流すだけなんていうことは、もはや珍しくなくなった。
問題はそれだけにとどまらない。現場上がりの解説者にしても、そのほとんどが結果論だけに終始し、また自分がそれまで在籍していた球団に気を使っているからなのか、本音でモノが言えなくなってしまっている。これは嘆かわしいを通り越して、もはや不安にしか思えない。
野球の評論、解説とは本来、1球ごとに生じる攻撃する側と守る側のせめぎ合いや心理戦、監督の采配の妙にポイントを当てて説明しなければならない。たんにホームランやヒットを打ったことや、三振を奪ったことなど、目に見えるものだけを追い求め、勝った負けたと一喜一憂しているようでは、外野スタンドで応援しているファンとなんら変わりがない。
この程度の解説しかできない人間がいざ監督やコーチなどユニフォームを着て現場に戻ったらどうなるのか。奥深い野球の追求など、到底あり得ないだろう。
さらに困ったことに、勝った負けたの結果ばかりを追い求めているのは、解説者だけではない。チームの運営を預かる球団オーナーや社長も同じなのである。
負けが込むと「監督の采配に問題があるのでは」などと疑心暗鬼になり、シーズン通してBクラス、あるいは最下位に沈んでしまうものなら、すぐさま監督、コーチを総取換えしてしまう。「監督やコーチを代えれば勝てる」と思い込んでいるのだ。
そうして後釜の監督やコーチのポストを狙っている解説者は、低迷しているチームのオーナーや社長にご機嫌を伺いながら、虎視眈眈とその座を狙っている。なんとも嘆かわしい限りだ。
私が現役時代だった頃、そして監督として現場復帰した1990年代と2000年代を振り返ると、今よりもっと面白い野球を繰り広げていたように思えて仕方がない。
野球は1球投げるごとに状況が変わるスポーツだ。そしてランナーが塁上にいれば、それだけで緊張感が増してくる。アウトカウントやボールカウントによってリードを巧みに変え、ランナーを牽制し、バッターをいかに抑えるかに気を配らなくてはならない。
ところが今の野球は違う。バッターを打ち取るにしても、考えてリードしているキャッチャーがどれだけいたのだろうか。あるいは味方のベンチが相手チームのサインを察知して、裏の裏をかくような野球をしていたチームがそれだけあったのかと聞かれれば、疑問符はとれない。2015年、12球団のキャッチャーでシーズン通してフル出場を果たしたのがヤクルトの中村悠平だけであることを考えると、考える野球を実践することなど、まず不可能と見て間違いない。
今のプロ野球はどうしてこうなってしまったのだろう。そこであらためて監督とはどういった人材に託すべきか、プロ野球に未来はあるのか。あらためて考察したいと思い、書き記してみた。
さらに言わせてもらえば、「いったいどうなってしまったんだ、プロ野球!」、この言葉こそ、私の偽らざる本音である。2015年のプロ野球を見ていて感じたこと、2016年シーズン以降に期待したいこと、それらについて、余すことなく語っていきたい。
【著者紹介】
1935年生まれ。京都府立峰山高校を卒業し、1954年にテスト生として南海ホークスに入団。現役27年間で、歴代2位の通算657本塁打、戦後初の三冠王など、その強打で数々の記録を打ち立て、不動の正捕手として南海の黄金時代を支えた。「ささやき戦術」や投手のクイックモーションの導入など、駆け引きに優れ工夫を欠かさない野球スタイルは、現在まで語り継がれる。70年の南海でのプレイングマネージャー就任以降、四球団で監督を歴任。他球団で挫折した選手を見事に立ち直らせる手腕は「野村再生工場」と呼ばれる。 ヤクルトでは「ID野球」で黄金期を築き、楽天では球団初のクライマックスシリーズ出場を果たすなど輝かしい功績を残した。インタビュー等でみせる独特の発言は「ボヤキ節」と呼ばれ、 その言葉は「ノムラ語録」として野球ファン以外にも親しまれている。
内容説明
セ弱パ強、シーズン途中の監督解任、オーナーの現場介入、選手兼任監督、プレミア12準決勝敗退…。問題や課題の多い今のプロ野球界に言えることは、監督の人材不足である。そもそも監督を育てるような環境が整っておらず、負けが込むと安易に監督を変えるようでは、いつまでたっても強いチーム作りは行えない。このような「監督受難」の時代に監督として必要な資質を、勝負と人間の機微を熟知した智将・野村克也が語る。
目次
第1章 間違いだらけの侍ジャパン監督選び(負けてはいけない試合で、小久保監督の采配のまずさが露呈した;嶋のリードは韓国側に読まれていた ほか)
第2章 12球団に本当の監督がいなくなった(かつての教え子たちが優勝を勝ち取ったヤクルト;原辰徳は名将とは言えない ほか)
第3章 私が仕えた4人の監督(南海を選んだ理由は「レギュラーに一番近かったから」;「ブルペン捕手として採用した」と伝えられ、愕然とした ほか)
第4章 監督に求められる資質(指導者たる者、言葉の引き出しを持っていなければならない;組織の力量は、リーダーの力量以上にはならない ほか)
第5章 「期待できる人材は若手にはいない」という現実(後継者を育てなかったことが、最大の後悔である;外野手出身者に名監督は少ない ほか)
著者等紹介
野村克也[ノムラカツヤ]
1935年生まれ。京都府立峰山高校を卒業し、1954年にテスト生として南海ホークスに入団。現役27年間で、歴代2位の通算657本塁打、戦後初の三冠王など、その強打で数々の記録を打ち立て、不動の正捕手として南海の黄金時代を支えた。「ささやき戦術」や投手のクイックモーションの導入など、駆け引きに優れ工夫を欠かさない野球スタイルは、現在まで語り継がれる。70年の南海での選手兼任監督就任以降、4球団で監督を歴任。他球団で挫折した選手を見事に立ち直らせる手腕は「野村再生工場」と呼ばれる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
マッちゃま
as
Kaz
ペカソ・チャルマンチャイ
Kaz