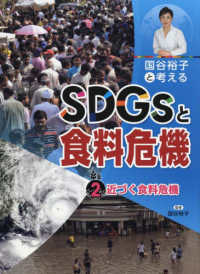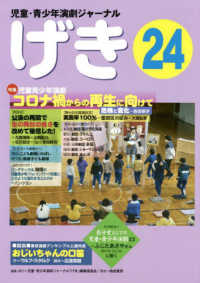出版社内容情報
難関大学の問題で学ぶ目からウロコの高校数学
前著『こんなふうに教わりたかった! 中学数学教室』に続く本書は、のべ100万人超の受験生を志望校とへ導いた元代々木ゼミナール伝説の数学講師である著者が、東大をはじめとする超難関大学の入試問題を例に、中学~高校2年生前半までの数学の基本事項で解く方法を丁寧に解説。「難関大学の問題もこうすれば簡単に解けるのか」という驚きとともに、納得感を得ることができる。大人の学び直しはもちろん、現役学生にも役立つ、高校数学の使い方・考え方を凝縮した一冊。
第1話 “ある1文字がとりうる値の範囲”を聞かれたらこうする
第2話 三角形の高さ(=垂線の長さ)が出てきたら、面積と結びつけて考える!
第3話 先に面積ありき。そこからいろいろな長さを求めるには?
第4話 三角形の問題、内部で解決策を見いだせなければ外へ目を向けよう
第5話 “もしかして二等辺三角形じゃないかな?”という目で見てみる価値あり
第6話 2平面のなす角。測る場所を間違えやすいので注意です!
第7話 等式の証明問題は、ぶれないことが大事です!
第8話 文字を入れ替えると相手の式になる連立方程式には、解法のパターンあり
第9話 方程式、関数、実数、虚数……それぞれの扱い方があります
第10話 体積を求めたいとき、都合のよい底面をあぶりだす発想
第11話 立体における“距離が等しい”を処理する方法
【著者紹介】
2010年度まで代々木ゼミナールの伝説の数学科講師として約30年間、のべ100万人超の生徒を志望校へ導く。代ゼミ退職後の今もオフィシャルファンサイトが開設されるほどの絶大な人気を誇る。現在は、教員研修・出張講義のための塾プロジェクトシアターゼミナール(PTS)を主宰。全国の高等学校・中学校に出張して教師や生徒の指導にあたる。県教育庁での講演も多く、県レベルでの教育水準アップに力を入れているほか、高等学校のカリキュラム改革にも定評がある。講義を聴講する生徒には社会人も多く、「生涯教育としての数学」の啓蒙に力を入れている。著書に『こんなふうに教わりたかった! 中学数学教室』(SBクリエイティブ)など。執筆協力:定松直子(さだまつ なおこ)女優としてテレビドラマや舞台などで活動する一方、夫である著者の右腕として、十数年にわたり数学や化学のテキスト等の執筆協力を行っている。
内容説明
東大、京大、一橋、早慶…難関大学の数学入試問題は、実は中学および高校2年生前半までの数学の基本事項さえ知っていれば、簡単に解けてしまう。元代ゼミ伝説の数学科講師である著者が、難関大学の過去の入試問題を取り上げ、丁寧に解法を解説。「こう考えればよかったのか!」と数学が身近に感じられ、学び直しの社会人、現役学生の心強い味方となる、数学の見方が変わる一冊。
目次
第1話 “ある1文字がとりうる値の範囲”を聞かれたらこうする(東京大学入試問題より)
第2話 三角形の高さ(=垂線の長さ)が出てきたら、面積と結びつけて考える!(一橋大学入試問題より)
第3話 先に面積ありき。そこからいろいろな長さを求めるには?(慶應義塾大学入試問題より)
第4話 三角形の問題、内部で解決策を見出せなければ外へ目を向けよう(東京大学入試問題より)
第5話 “もしかして二等辺三角形じゃないかな?”という目で見てみる価値あり(京都大学入試問題より)
第6話 2平面のなす角。測る場所を間違えやすいので注意です!(東京大学入試問題より)
第7話 等式の証明問題は、ぶれないことが大事です!(早稲田大学入試問題より)
第8話 文字を入れ替えると相手の式になる連立方程式には、解法のパターンあり(東京大学入試問題より)
第9話 方程式、関数、実数、虚数…それぞれの扱い方があります(京都大学入試問題より)
第10話 体積を求めたいとき、都合のよい底面をあぶり出す発想(東京大学入試問題より)
第11話 立体における“距離が等しい”を処理する方法(東京大学入試問題より)
著者等紹介
定松勝幸[サダマツカツユキ]
2010年度まで代々木ゼミナールの数学科講師。代ゼミ退職後、現在は、教員研修・出張講義のための塾プロジェクトシアターゼミナール(PTS)を主宰。全国の高等学校・中学校に出張して教師や生徒の指導にあたる。県教育庁での講演も多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
izumasa57
Enzo Suzuki
totssan
きざはし
Mark X Japan
-
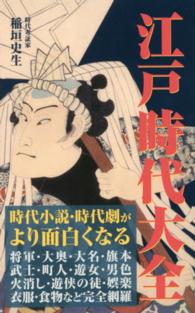
- 和書
- 江戸時代大全