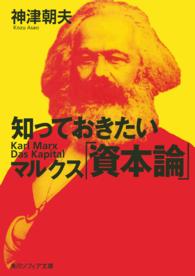- ホーム
- > 和書
- > 法律
- > 民法
- > 物権法・財産法・債権法
出版社内容情報
多当事者間での利得調整の法理とその関連論点を考察し、その意義を根本的に問い直し、将来の法定債権法改正に生かす必読書。不当利得の意義を根本的に問い直し、将来の法定債権法改正に生かす必読書。債権法改正で、契約の清算(給付利得)にかかわる規定が、民法、消費者契約法、特定商取引法に導入されようとしている中、多当事者間での利得調整の法理とその関連論点を考察し、その意義を根本的に問い直す。
『不当利得法理の探究(学術選書182)』
平田健治(大阪大学大学院法学研究科教授) 著
【目 次】
◆第1章 問題提起◆
◆1 ドイツ法における賃借人の費用償還請求権
はじめに
? 問題の所在―ケメラーの見解
? 費用の概念
第1節 連邦裁判所(BGH)の2判決
? BGH1953年7月10日第五民事部判決
? BGH1964年2月26日第五民事部判決
? 2判決の位置づけ
? 学説の分布
? 問題状況
第2節 学説の検討と償還を認めた判決例の類型化
? 学説の検討
? 判決例の類型化
第3節 有益費償還の判断基準としての事務管理法
? 事務管理による費用償還の要件
? 現実の運用
? 一般利得法への還元
? 沿革からの理解
おわりに
◆第2章◆転用物訴権とその周辺
◆2 フォン・トゥールの「転用物訴権」論について
第1節 フォン・トゥールの「転用物訴権」論の課題
? 日本法での現状
? 「転用物訴権」論の課題
第2節 「転用物訴権」論の出発点
? 従来の諸見解
? 求償権への注目
第3節 転用物訴権の成立の前提としての,求償権の成立
? 事務処理の一般概念
? intercessio
第4節 「免責請求権」の諸特性
? 体系上の地位
? 免責請求権の成立
? 免責請求権の債務負担に対する依存性
? 履行の諸態様
? 相 殺
? 免責請求権の移転可能性
? 免責請求権の差押可能性
? 破産財団の積極財産としての免責請求権
第5節 転用物訴権の基礎としてのintercessio,利得説との対決
? 転用物訴権の基礎としてのintercessio
? 利得説との対決
第6節 転用物訴権の根拠づけ・要件・効果
? 根拠づけ
? 要 件
? 効 果
第7節 準転用物訴権の根拠づけ・要件・効果
? 根拠づけ
? 要 件
? 効 果
? トゥールが最終的に目指したもの(立法論)
第8節 トゥールの「転用物訴権」論の与える示唆・その評価
◆3 ドイツ法における請負人修理事例が日本法に与える示唆―転用物訴権の可否
はじめに
第1節 ドイツ民法の所有物返還請求における占有者の(いわゆる所有者占有者関係における)
費用償還請求権関連規定の立法過程
? 前史―部分草案
? 実体的内容
? 権利行使方法
? 小 括
第2節 ドイツ判例における展開
第3節 日本法における議論
◆4 〔判例研究〕建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に
建物所有者に対し不当利得の返還を請求することができる場合
〔判決要旨〕
〔事 実〕
〔判決理由〕
〔研 究〕
◆第3章◆多当事者をめぐる利得調整の諸問題
◆5 ドイツにおける三当事者不当利得論の近時の展開―判例における給付概念の意義の相対化
第1節 はじめに
第2節 学説の今日までの流れの概観
? はじめに
? 通説的類型論の成立まで
? 三当事者関係における給付概念の機能(カナーリスによる通説批判)
? 三当事者関係における要件・効果の観念化,効果転帰の構造
第3節 判例の今日までの流れの概観
第4節 近時のBGH四判決の紹介と分析
? はじめに
? 事案内容の紹介
? 判決の分析
? 判断モデル相互の限界づけ
第5節 まとめ
◆6 第三者与信型割賦販売契約の解消と清算方法―割販法改正による清算規定の位置づけ
はじめに
第1節 2008年割販法改正に至るまでの状況
第2節 2008年改正の概要
第3節 2008年改正内容の検討
第4節 学説における解釈
第5節 ドイツ法の状況
第6節 検 討
◆7 〔判例研究〕第三者の強迫による金銭消費貸借の取消しと清算関係
〔判決のポイント〕
〔事 実〕
〔判決理由〕
〔研 究〕
◆8 〔判例研究〕共同相続人の一部への預金全額の払戻しと不当利得
〔判決要旨〕
〔事 実〕
〔判決理由〕
〔研 究〕
◆9 〔判例研究〕?金銭の不当利得の利益が存しないことの主張・立証責任,
?不当利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅と返還義務の範囲
〔判決要旨〕
〔事 実〕
〔上告理由〕
〔判決理由〕
〔研 究〕
◆10 所有者・占有者関係における他主占有者の位置づけ―他人の物の賃貸借での使用利益返還義務を素材として
第1節 はじめに
第2節 ドイツ民法の起草過程と施行後の判例・学説
第3節 フランス法と日本民法の起草過程
第4節 日本の判例と学説
第5節 おわりに
◆第4章◆双務契約の清算
◆11 無効・取消しの効果
第1節 同時履行の抗弁権の成否
第2節 果実・使用利益の返還義務
第3節 給付物の滅失・損傷の場合の処理
第4節 片務契約・無償契約・利用契約の場合
◆12 制限行為能力者の返還義務についての特則
第1節 問題の所在
第2節 沿革からの解明
第3節 現行法の解釈
◆第5章◆いわゆる騙取金銭の法理
◆13 「騙取金銭による弁済と不当利得」覚え書き
第1節 判例のおおよその流れと学説の影響
第2節 判例に現れた事案類型
第3節 学説に現れた二方向(取消権構成と即時取得構成)
第4節 学説が依拠する二制度と金銭騙取事案との制度目的・要件に関するずれ・距離
第5節 無資力要件の構成上での位置づけ方
第6節 無資力と価値の同一性(特定性)との関係
第7節 若干の検討
◆14 金銭騙取事例における第三者弁済類型の位置づけ
第1節 はじめに
第2節 我妻説における第三者弁済型
第3節 その後の学説,とりわけ類型論における第三者弁済型
第4節 第三者弁済型における価値追及の構造
◆第6章◆利得者の主観的態様
◆15 民法704条後段の沿革
第1節 発端としての最高裁判決
〔事 実〕
〔判決理由〕
第2節 沿革の探求
? 本判決の位置づけ
? 民法704条の審議
? フランス民法から旧民法へ
? ドイツ民法草案からの潮流の融合
? 改正の方向
◆16 〔判例研究〕貸金業法17条1項に規定する書面の交付の有無及び貸金業者が受領した貸金業法43条1項の
適用されない制限超過利息の返還における悪意の推定
〔事 実〕
〔判決理由〕
〔研 究〕
◆17 〔判例研究〕期限の利益喪失特約の下での制限超過利息の支払の任意性を否定した最高裁判決以前に
おける「悪意の受益者」推定
〔事 実〕
〔判決理由〕
〔研 究〕
◆第7章◆特殊問題
◆18 〔判例研究〕法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者が利得した物を第三者に売却処分した
場合に負う不当利得返還義務の内容
〔事 実〕
〔判決理由〕
〔研 究〕
◆19 〔判例研究〕ネズミ講運営会社の破産管財人から配当金受領者に対する返還請求は不法原因給付として否定されるか
〔事 実〕
〔判決理由〕
〔研 究〕
◆20 〔判例研究〕破産管財人の善管注意義務違反と不当利得―最高裁平成18年12月21日2判決の枠組の再検討
〔事 実〕
〔研 究〕
〔まとめ〕
事項・人名索引
平田 健治[ヒラタ ケンジ]
著・文・その他
内容説明
多当事者間での利得調整の法理の模索と関連論点。不当利得の意義を根本的に問い直し、将来の法定債権法改正に生かすためにも、必読の書。
目次
第1章 問題提起
第2章 転用物訴権とその周辺
第3章 多当事者をめぐる利得調整の諸問題
第4章 双務契約の清算
第5章 いわゆる騙取金銭の法理
第6章 利得者の主観的態様
第7章 特殊問題
著者等紹介
平田健治[ヒラタケンジ]
1953年岐阜県生まれ。1976年京都大学法学部卒業。1981年京都大学大学院法学研究科博士課程修了、京都大学助手。1984年新潟大学法学部助教授。1991年同教授。1997年大阪大学大学院法学研究科教授(2004年より2012年までは高等司法研究科)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
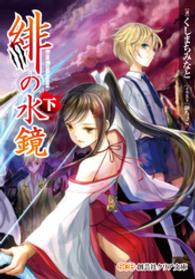
- 電子書籍
- 緋の水鏡 <下> 創芸社クリア文庫
-
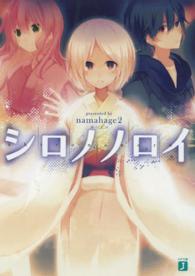
- 和書
- シロノノロイ MF文庫J