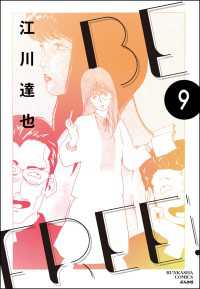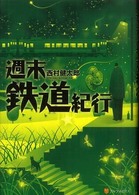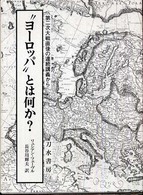目次
1 総説(日本民法典編纂史の捉え方;日本民法典編纂史とその資料―旧民法公布以後についての概観)
2 民法前三編(総則・物権・債権)の成立(第九回帝国議会の民法(前三編)審議
『民法中修正案』(前三編の分)について
民法(前三編)の理由書に関する序論的考察)
3 民法後二編(親族・相続)の成立(第一二回帝国議会の民法(後二編)審議
『民法中修正案』(後二編の分)について)
4 民法史断想(六法にみる不注意;『以活版換謄写/民法修正案理由書』の原資料について―『第九回帝国議会の民法審議』(一九八六年、有斐閣刊)への序
『未定稿本/民法修正案理由書』の有用性について―『民法修正案(前三編)の理由書』(一九八七年、有斐閣刊)への序
幸運だった民法典
帝国議会議事速記録の復刻について
梅文書目録に期待する
学振版議事録の異同
旧民法の公布年月日
民法改正立法の過誤
民法改正立法の過誤(再論)―政府見解の誤謬について
梅文書に含まれる貴重資料あれこれ―『法政大学図書館所蔵梅謙次郎文書目録』(二〇〇〇年)への序
民商法修正案の起草
「第一編 人」で始まる新しい民法典の編纂―将来「日本民法史の一齣」となることを期待した二〇〇八年の「提案」)
5 私の民法典編纂史研究(民法の講義に利用する資料の調査・研究としての出発―民法修正暗(前三編)に関する旧稿(一九八七年)のはしがき
純粋な歴史研究としての民法典編纂史研究へ―『日本民法典資料集成』第一巻(二〇〇五年)あとがき)