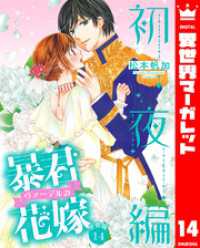出版社内容情報
フーコー、ドゥルーズ、バルト、ロブ=グリエ等フランス現代知の戦略的導入をいち早く試みた本書は、著者の提示する表層批評の原点を示し、何よりも絶好の現代思想入門たりえている
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
13
単行本デビュー作。当時は日本からの興味の視線も強かったであろうフランスの知の相貌の現地紹介者を、著者は居心地悪そうに引き受ける。同時に、お前らが求めてる「知識」なんてここにはないんだ、そんな「知識」が崩れる地点で初めて「知」は現れるんだということを、文体自体で感得せしめんとする。蓮實重彦のトレードマークと目される「テマティズム」を、本人はここで両義的に、というか少し批判気味に記している。ドゥルーズ、ロブ・グリエ、フーコー、バルトとの会話の記録が、やはり一番の白眉か。蓮實を絶賛するバルトが微笑ましい。2021/12/28
シッダ@涅槃
12
「表層」つまりそれは「宇宙=闇」。「隠された起源なり真実なりをほのめかしながらわれわれに探求の姿勢を促すあの深遠、壮麗、秘境といった概念とは根源的に異質の、背後ともに彼方とも違う、いわば尺度を持たぬ距離とでもしようか、とにかくたがいの表面にまといつく未知の触覚のみによって、平坦な外殻との環境の微妙な差異をもの語ることしかしない、濃密な闇のそのもの(以下略)」。◆インタビューでのフーコーの“ドストエフスキー笑い”(へっへっへっ)には爆笑してしまった笑。やや難解なのでいかめしく読みがちだが、エンタメです。2025/07/15
Don2
8
蓮實先生の本を初読みなんだけど、本書はフランス哲学・文学者の本の分析+本人へのインタビュー集だったので、結果、知らない人が知らない人と知らない作品について話すのを読む感じになってしまった。とはいえ、批評部分は蓮實先生の流れるような文体と、インタビューの中で交わされる問題意識が新鮮で面白かった。いわゆる分析哲学が、事件を言葉の中に閉じ込めた後の整合性を議論するのに対し、当時の文学は"出来事"の個別性を"ことば"という型にはめることによる暴力性を議論している。面白い。2025/08/24
♨️
4
少しでも著作を読んだことあるドゥルーズ、フーコー、バルト論(およびインタビュー、贅沢!)に関していえば、すごく素直にキーモチーフをついている気がして(インタビューで各々の人物に褒められてるのをそのまんま載せているのが良い笑)、これらの人物についてはそのことこそが、批評家としての面目躍如になっていることが面白かった。例えば、ドゥルーズならば「と」(「差異と反復」「資本主義と分裂症」)であり、フーコーならばフーコーの実践については「知」「権力」の枠組みからどう捉えられるのかであり、2021/07/03
小川一輝
4
ドゥルーズ、ロブ・グリエ、フーコー、バルト、リシャールと名前を聞くだけで面倒くさい面々に対する蓮實重彦によるテキスト批評。本当に読めたのか些かの自信もないのだけれど各人のテキストが想起させる空間、質量、時間、欲望、運動をどこか滑りのある手際で抽出していく。文学に付き纏う「深さ」や「思想」を読み手の怠慢と捏造であるという批判は最初に接したときはまさに!と膝を打った。テキストは書き手からは独立して存在し読み手に作用するのでは?と種々の評論を読みながら疑問に思っていた身としてはまさに福音だった。2018/03/03