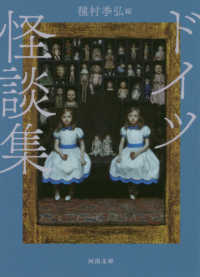内容説明
瓦は屋根の上にあるものではなく、空手のパフォーマンスで割られるもの。ミスターといえば長嶋茂雄ではなく鈴井貴之。リーダーは渡辺正行ではなく森崎博之。ネット通販の送料の高さに納得がいかない。公的文書や各種申込書に住所を書く際、北海道と書いたあとに都道府県の「道」を丸で囲む。おせち料理を食べると「今年も終わりだなぁ」と思う。スギ花粉症の辛さがわからない。道民ならではのご当地ネタ300発。
目次
第1章 本音・実態あるある
第2章 郷土愛あるある
第3章 上京あるある
第4章 常識あるある
第5章 気候・風土あるある
第6章 テレビ・芸能あるある
第7章 グルメ・名物・名産あるある
著者等紹介
岡田大[オカダダイ]
1974年、東京生まれ。大学卒業後、9年間の出版社勤務を経てフリーに転身。編集者・ライターとして、スポーツ・ギャンブル・グルメを中心に、さまざまなジャンルの企画に携わり、書籍・雑誌・WEBで編集および執筆活動を精力的に行っている。競馬コミュニティサイト『ウマニティ』の編集長も務め、イベントの司会業もこなす(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Miyoshi Hirotaka
29
北海道には歴史上、二度の人口流入期がある。最初は、ロシアとの樺太・千島交換条約による国境確定後50年間。二回目は戦後の約15年間。北海道の文化は多様な地域からの人口流入の影響を強く受けた。今年は北海道と命名されてから150年。わが国の他地域の歴史と比べれば全く新しい。にもかかわらず、北海道人というアイデンティティは形成された。しかも、文化は受容した方が元の形を残すという法則も作用した。また、自分達に都合のいいものを取捨選択し、カスタマイズするというわが国の特性も発揮されている。文化の実験場として興味深い。2018/03/26
るんるん
26
まあ、なんとなく読んだんで、細かい文は読まなかったけど。なんというか世代であるある度が変わる本だと思う。水曜どうでしょうも見たことないし、ススキノを知ったときにはもうラフィラだったし、まあ当たってるのもあったけどな。星澤先生の料理とサッカーで優勝したよ。は当たってたな。未だに美味しそうに見えないんだよな。星澤先生の料理。2015/02/06
biba
19
どうでしょうネタが多いところが、まさに北海道って感じ。こういう本が好きで読んじゃうところが、さすが「道産子」!北海道愛にあふれてるなーって自分で思ってしまいます。2013/01/28
むーちょ
17
何度か笑った(驚いた)の一つに盆踊りの「ちゃーんこちゃーんこちゃんこちゃちゃんがちゃん」(;゚Д゚)家族みんなで「えーーーーーー!!!!」ってなりました。セイコーマートも北海道にしかないと思ってたし。2013/03/07
あじつ
12
サッカーで優勝したよ。2014/04/09