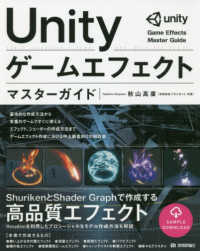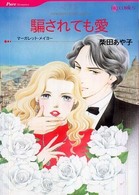内容説明
東京は中央線、高円寺で降り、少し行くと、古風な風情をかもし出している店がある。「古本酒場コクテイル」。今夜も、古本と酒とおしゃべりが大好きな人で一杯だ。そんな古本酒場を舞台にした人と人の交流を温かく描く。
目次
1 店長日記(二〇〇六年;二〇〇七年;二〇〇八年)
2 一九九八年春・国立で(退職金も貯金もなかったが、ただ熱い思いだけがあった)
3 二〇〇〇年秋・高円寺に(この店から、何かを発信してみようと思った)
4 二〇〇四年冬・高円寺あづま通り(「あんたは若い。後悔するなよ」。棟梁のその言葉は忘れられない)
5 中央線・古本屋のひと(悠山社書店橋本さん;島木書店鈴木さん)
著者等紹介
狩野俊[カリノスグル]
1972年福島県生まれ。洋書店勤務を経て、98年、東京・国立に「コクテイル書房」を開業。半年後に店の一部を改装し酒を出し始める。2000年、高円寺へ移転。「古本酒場コクテイル」を営む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
onasu
14
このお店、発見してはいたのですが、未踏。閉まっていたので、定休日かと。後日、読んだ本で酒場を兼ねた夜営業のお店だと知って、次いで偶然、図書館で店主さん著のこの本を。読み始めたら、読了したばかりの久住昌之氏が頻出、て繋がり方に感心しきり。 中身は、お店日記と開店、2度の移転話しなど。後者の経緯は、おもしろい。ただ、この手のもの、倉敷の蟲文庫 田中美穂さんのものを読んでいて、それと比べてしまうと、構成が今いち、誤字も多い。 まずは行ってみて、とネット検索したら、不幸のため、しばらくお休み。またして残念!2013/05/30
sawa
9
★★★☆☆ 高円寺の古本居酒屋「コクテイル」店主の本。前半の日記は、知ってる古本屋店主とか、作家が出てくるから、面白いという程度。後半の仕事を辞めて、国立で最初の「コクテイル」を作り、高円寺へ移転し、という話が面白い。店も開けずに朝から酒を飲み、時代劇専門チャンネルを見ながら泣く、借金しながらも酒を飲み続ける。3軒目のお店を作る際の、シルバー人材センターの元大工のじいさんとの話。まるで小説のようなエピソードの数々に引き込まれる。久しぶりに飲みに行きたい。(図)2012/05/26
しおり
6
まず、古本酒場という題名に惹かれました(笑)。作者さんの開くお店が、古本屋から古本酒場へと形態を変えていき、そこに集まる人々との繋がり(主にお酒の(笑))が、日記として綴られていました。大変な時期もあったけれど、作者狩野さんの人徳か、ハタマタ幸運か…?(笑)。人情味溢れる人々に恵まれて、古本酒場は魅力ある社交場となったみたいです。私も是非伺ってみたいものです!2015/02/19
owlsoul
5
「文化人」という言葉には、洗練されたハイソな人々を連想させるような、どこかお高くとまった響きがある。しかし、本当の意味で文化に生きる人々は、世間の目も顧みず、日々の暮らしに困窮しながらも自分の好きなこと・信じたものに時間と金を費やすような、どちらかというと夢追い人や道楽者といった存在に近い。本書では、そんな極めて素朴な「文化人」の日常の一端が垣間見れる。古本と酒場を愛する中年男が「古本酒場」を開店し、軌道にのせるまでの奮闘記。自分の店に生きがいを感じながらも、ふと将来への不安をよぎらせる著者の言葉が沁みる2022/08/20
furugenyo
3
高円寺「コクテイル」の店主が綴る、前半は日記(ブログ)、後半はお店を始めた当時のことなどを書いた本。 後半も興味深いけど、日記の東太后と西太后の話もおもしろかった。「いい歳を経た、それなりに苦労して生きてきた女性に」は敵わないと思う。まったく。2010/09/04
-

- 和書
- 懐かしの愛唱歌集